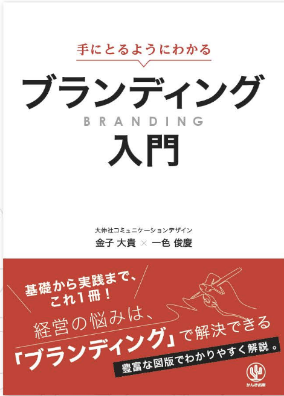「リブランディング」とは、企業や製品が時代の変化に適応するために、ブランドの再構築をすることです。新たな市場を開拓し、競争力を強化するための手段として、多くの企業が取り組んでいます。
しかし、ブランディングやリニューアルとの違いや取り組み方を正しく理解しなければ、期待する効果が得られないこともあります。
そこで本記事では、リブランディングの意味や種類、メリット・デメリット、成功のポイントについて詳しくまとめました。具体的な成功事例も紹介するので、リブランディングを検討している方は参考にしてください。
- 目次
リブランディングの意味は?

リブランディングとは、「既存のブランドを見つめ直し、市場のニーズや時代に合わせて再構築すること」を意味します。企業や製品、サービスを見直し、ブランドの価値を高めるために行われます。
以下ではリブランディングの意味について、ブランディングやリニューアルとの違いも踏まえて解説します。
リブランディングとブランディングの違い
ブランディングは、企業や製品が市場で独自の価値を確立し、顧客との信頼関係を築くためのプロセスです。一方、リブランディングは、既存のブランドを市場の変化に合わせて再構築することを意味します。
つまり、ブランディングは「ブランドを作ること」、リブランディングは「ブランドを再定義すること」といえます。
リブランディングとリニューアルの違い
リニューアルとは、既存製品のデザインや機能を改善し、印象やメッセージを刷新することを意味します。
リブランディングでは、企業の理念やターゲット層の見直しなども行います。これに対してリニューアルでは、製品のロゴやパッケージの変更などに留まります。リニューアルはリブランディングの一環として行われることもありますが、ブランドの本質を変えるものではありません。
リブランディングの種類

以下では、リブランディングの種類について見てみましょう。リブランディングには、「コーポレートブランディング」と「製品(サービス)ブランディング」の2種類があります。
コーポレートブランディング
企業全体のブランドイメージを見直すのがコーポレートブランディングです。コーポレートブランディングでは、企業の全体的なアイデンティティを見直し、経営理念や企業文化を再定義します。
経営方針の転換や市場環境の変化に合わせて実施されることが多く、ロゴやスローガンの変更、社名の変更を伴うこともあります。
コーポレートブランディングによって企業の価値観や目指す未来が明確になり、社員のモチベーション向上や一致団結を促進します。
関連記事:自社、顧客、従業員が求める「コア」が独自のブランドをつくる。
製品(サービス)ブランディング
特定の製品やサービスのブランドイメージを再構築するのが製品(サービス)ブランディングです。製品(サービス)ブランディングでは、市場のトレンドや消費者ニーズに合わせて、USP(Unique Selling Proposition:独自の売り)を明確にすることが重要です。
従来の製品との差別化によりブランドの価値を向上させることで、市場での競争力を高めるために行われます。
リブランディングのメリット

ここからは、リブランディングのメリットについて解説します。リブランディングのメリットは以下のとおりです。
- 市場開拓ができる
- ブランド価値が向上する
- 社内の活性化につながる
- 競合他社との差別化ができる
- 顧客ロイヤルティが強化される
市場開拓ができる
1つ目のメリットは、市場開拓ができることです。新しいブランド戦略を取り入れることで、これまでリーチできなかった顧客層へのアプローチが可能となります。
デザインやメッセージを刷新することで新たな顧客層を獲得できれば、市場での競争力をさらに高められます。売上の増加や、新しい市場への進出を実現できるでしょう。
ブランド価値が向上する
2つ目のメリットは、ブランド価値が向上することです。既存ブランドが築いてきた資産を活かしつつ、時代に合ったブランドへと変化させることで、新しい価値を付与できます。
ブランドイメージが刷新されることで認知度や信頼度が向上し、顧客との関係性を強化できます。市場のニーズを反映したブランドは消費者の共感を得やすくなり、長期的な成長にもつながるでしょう。
社内の活性化につながる
3つ目のメリットは、社内の活性化につながることです。新しいブランド戦略の導入により、従業員のモチベーション向上やエンゲージメント強化が期待できます。
社員が新しいビジョンや戦略に共感し、一丸となって取り組むことで、企業全体の活性化が図れます。経営層だけでなく現場のスタッフもブランドの方向性を共有することで、組織全体の一体感が生まれるでしょう。
競合他社との差別化ができる
4つ目のメリットは、競合他社との差別化ができることです。競争が激しい市場では、他社との差別化が欠かせません。
リブランディングで独自の強みを明確にして、魅力を強く発信することで、自社の競争力を高められます。消費者に対して「なぜこのブランドを選ぶべきか」を明確に示し、競合との違いを際立たせることができます。
顧客ロイヤルティが強化される
5つ目のメリットは、顧客ロイヤルティが強化されることです。リブランディングにより、顧客のニーズに沿った価値や体験を提供することで、顧客満足度が向上します。
顧客がブランドの新しい価値を認識し、より愛着を持つようになることで、リピート率の向上や口コミによる拡散も期待できます。
リブランディングのデメリット

リブランディングのデメリットは、以下のとおりです。
- コストが増大する
- リスクが増加する
- 長期的な取り組みが必要となる
- やり方を誤れば効果が出ないリスクもある
コストが増大する
1つ目のデメリットは、コストが増大することです。リブランディングでは、デザイン変更や広告キャンペーン、新たなマーケティング戦略の策定など、多くの費用が発生します。ロゴやパッケージデザインの変更だけでなく、ウェブサイトの改修や販促ツールの作成なども必要になる場合があります。
特に大企業の場合、ブランドガイドラインの更新や従業員教育などにもコストがかかるでしょう。費用対効果を慎重に見極めなければなりません。
リスクが増加する
2つ目のデメリットは、リスクが増加することです。リブランディングによりブランドイメージを刷新することで、既存の顧客が離れてしまうリスクがあります。
長年愛されてきたブランドのデザインやコンセプトが急激に変わると、従来の顧客が違和感を持つかもしれません。また、社内の理解を得られないままリブランディングを進めると、従業員の混乱を招く場合もあるため注意が必要です。
長期的な取り組みが必要となる
3つ目のデメリットは、長期的な取り組みが必要となることです。ブランドの再構築には時間がかかり、即効性がない場合があります。
ロゴやデザインを変更するだけではなく、新しいブランドイメージを消費者に浸透させるためのマーケティングやPR活動が不可欠です。短期間で結果を求めすぎると、十分なブランド浸透が進まないまま、再び方向転換を余儀なくされる可能性もあります。
関連記事:ブランディングとマーケティングの違いとは?関係性や成功事例を紹介
やり方を誤れば効果が出ないリスクもある
リブランディングが成功するかどうかは、戦略の立て方次第です。市場や消費者のニーズを的確に把握せずにブランドを変更すると、期待した効果が得られないこともあるでしょう。特に、ブランドの核となる価値やアイデンティティを無視して変更すると、消費者の共感を得られません。かえって、ブランドの価値を損なってしまうリスクもあります。
リブランディングでブランドの本質を再構築するために、市場調査やターゲットの分析は入念に行う必要があります。
リブランディングが必要なタイミング

以下では、リブランディングが必要なタイミングについて解説します。以下のような動きが見られたら、リブランディングを検討するとよいかもしれません。
- ブランドの陳腐化
- 競争力の低下
- ビジネス環境の変化
- 経営者の交代
ブランドの陳腐化
長年使用してきたブランドが新鮮さを失って売上が低迷している場合、リブランディングが必要になります。例えば、ロゴやパッケージデザインが古く見える、企業のメッセージが現代の価値観とずれているといったケースです。
こういったケースでは、市場や消費者のニーズの変化に対応するためにブランドの再構築が必要です。
競争力の低下
競合が次々と新しいブランドイメージを打ち出している場合、自社のブランドが時代遅れに感じられることがあります。このような場合は、自社ブランドの歴史や強みを活かしつつ、自社ならではの価値を見出すことがポイント。
他社とは違う特徴やメッセージを取り入れ、デザインや発信内容に反映させることで、新たな価値を生み出しましょう。
ビジネス環境の変化
市場のトレンドや消費者の価値観が大きく変わった場合も、従来のブランドでは対応できなくなることがあります。新しい技術や市場の変化に対応するために、ブランド戦略の見直しが必要です。
経営者の交代
新しい経営者が就任して企業の方向性が大きく変わる場合も、リブランディングのタイミングであるといえます。特に、創業者から次世代の経営者へバトンタッチされるタイミングでは、ブランドの刷新が求められることがあります。
また、M&A(企業買収・合併)によって企業のビジョンや事業内容が変わる場合も、ブランドの統一や刷新が必要となるでしょう。
リブランディングで見直す内容

リブランディングでは、ロゴやデザインの変更も大切です。しかし、プロジェクトを成功させるには、ブランドの根本から見直すことが重要です。
ここでは、リブランディングで特に注目すべき3つのポイントについて解説します。
- 製品やサービスの内容
- 市場におけるポジショニング
- ターゲット層
製品やサービスの内容
リブランディングでは、提供している製品やサービスそのものの見直しが欠かせません。市場のニーズや競争環境が変化している場合、従来の提供価値が時代遅れになっている可能性があります。ブランドの方向性に合わせて製品やサービスを見直すことで、新たな市場の開拓も実現できます。
市場におけるポジショニング
市場の中でブランドがどのような立ち位置にあるかを把握し、必要に応じてポジショニングを変更することも検討しましょう。
例えば、高価格帯の製品として認知されていたブランドが、中価格帯の市場にも参入し新たな顧客層を獲得するケースがあります。あるいは、低価格志向から脱却し、プレミアムブランドとしての地位を確立することで、ブランド価値を高める戦略もあるでしょう。
ターゲット層
ターゲットとする顧客層の見直しも行いましょう。特定の層に固執せず、柔軟な視点で他のターゲット層へのシフトや拡大を検討することが大切です。例えば、シニア向けのヘルスケアブランドが、30代・40代の健康意識の高い層へのアプローチも取り入れたケースがあります。
ターゲットが変わることで使用する広告媒体やコミュニケーションチャネルも変わるため、戦略全体の見直しも併せて実施しましょう。
関連記事:インサイトとは?
リブランディングの進め方│コーポレートブランディング

リブランディングの進め方について、コーポレートブランディングと製品(サービス)ブランディングに分けて解説します。
まずは、コーポレートブランディングにおけるリブランディングの進め方を見てみましょう。
- 現状分析
- ブランド戦略の策定
- 新ブランドの浸透
- 施策の実行
現状分析
リブランディングを進める前に、まずは現状を正確に把握することが重要です。現在のブランドが市場や顧客にどのように認識されているかを調査し、ブランドの強みや課題を洗い出しましょう。具体的には、以下のような方法で分析を行います。
- 市場調査(競合他社との比較、業界のトレンド分析)
- 消費者調査(既存顧客へのアンケート、口コミやSNSの分析)
- 社内ヒアリング(社員のブランド理解度や、現場の意見の集約)
上記のような調査結果から、消費者のニーズや期待に応えるブランド戦略を策定しましょう。
なお、顧客が評価しているポイントと、自社が強みと認識している部分にギャップが生じていることはよくあります。このギャップの是正を行っていくことが、ブランディングの重要なポイントとなります。
ブランド戦略の策定
次に、企業全体の方向性や戦略を決定し、ステークホルダーとの信頼関係を強化しましょう。ミッションやビジョンをもとに、新しいブランドアイデンティティを確立します。
市場のニーズに合わせるだけでなく、企業が本来持つ価値や強みを活かしたブランドを作ることが成功の鍵となります。
新ブランドの浸透
ブランド戦略の策定を終えたら、新たなブランド戦略を社内外に浸透させましょう。リブランディングでは外部向けの施策だけでなく、従業員の理解と共感を得ることも不可欠です。
社員一人ひとりが新しいブランドの意義を理解し、体現できるようにすることが重要です。社員の協力を得るためには、研修やワークショップを開催すると効果的でしょう。
施策の実行
ブランド戦略の策定と浸透が完了したら、具体的な施策を実行していきます。施策には以下のようなものがあります。
- ロゴ・スローガンの刷新(ブランドの視覚的な統一)
- 広告・プロモーションの展開(新しいブランドの認知拡大)
- 製品やサービスの改良(ブランドコンセプトに合わせた変化)
- PR戦略の実施(メディアへの露出、企業ストーリーの発信)
施策を実行した後は結果を評価し、課題があれば改善策を講じましょう。
リブランディングの進め方│製品(サービス)ブランディング

製品(サービス)ブランディングのリブランディングでは、特定の製品やサービスの価値を再定義し、市場のニーズに適応させることが目的です。ここでは、製品(サービス)ブランディングのリブランディングの進め方について詳しく解説します。
- 現状分析
- ブランド戦略の策定
- 新ブランドの浸透
- 施策の実行
現状分析
まず、製品やサービスの現状を分析し、市場の変化や競争環境を把握します。具体的には、以下のような分析を行います。
- ペルソナとカスタマージャーニーの確認(ターゲット顧客の明確化)
- 市場調査(競合製品との比較、トレンド分析)
- 既存ブランドイメージの評価(消費者調査、SNSの評判分析)
- 社内ヒアリング(社員の意見の集約)
ブランド戦略の策定
現状分析の結果をもとに、新しいブランド戦略を策定します。製品(サービス)ブランディングにおいては、消費者が求め、競合他社が実施できない自社独自の強み(SUP)を創出することが重要です。競合他社との差別化ポイントを見極めて、どのように消費者へ伝えられるかを検討しましょう。
新ブランドの浸透
製品(サービス)ブランディングにおいても、まずは新しいブランドを浸透させることが欠かせません。全社員がリブランディングの意図や意義を理解し、積極的に取り組めるよう、必要に応じて研修やワークショップを開催しましょう。
施策の実行
最後に、新しいブランドコンセプトを市場に浸透させるための施策を展開します。まずは顧客のブランド体験を重視し、視覚的・感覚的に「新しさ」を伝えることが大切です。例えば、以下のような施策が挙げられます。
- パッケージデザインの変更(新しさを伝える視覚的アピール)
- プロモーションの強化(SNSキャンペーン、インフルエンサー活用)
- 店舗でのブランディング強化(POPやディスプレイの刷新)
- ストーリーテリングの活用(ブランドの背景や理念の発信)
策定したブランド戦略を実行した後は、必ず効果を測定し、必要に応じて調整を行います。消費者の反応を見ながら、ブランドの浸透度をチェックすることが重要です。
リブランディングを成功させるポイント

以下では、リブランディングを成功させるポイントをご紹介します。
- 顧客理解とCX(顧客体験)の把握
- インサイトの把握
顧客理解とCX(顧客体験)の把握
リブランディングを成功させるために、まずは顧客のニーズや期待を正確に把握することが欠かせません。顧客のニーズや期待に基づいたブランド戦略を策定することで、顧客とのエンゲージメントを強化しましょう。
また、CXの向上により、顧客満足度を高め、ブランドロイヤルティを築くことが重要です。CXの改善には、顧客のフィードバックを積極的に収集し、製品やサービスに反映させることが求められます。
インサイトの把握
自社の強みと世間の評価を一致させるためには、顧客インサイト(顧客の声)を把握することが大切です。市場調査や顧客のフィードバックを活用し、ブランドに対する認識や期待を正確に理解しましょう。その情報をもとにブランド戦略を見直すことで、より魅力的で共感を得られるブランドを築けます。
インサイトの把握には、市場調査や一律的なアンケートだけでなく、ロイヤリティの高い顧客の声を細かに聴くことが効果的です。とはいえ、顧客に対して「わが社のイメージは?」「わが社の長所は?」と質問しても、とっさに答えられる方は少ないでしょう。聞き方にも工夫が必要なため、自社で顧客の声(インサイト)が聞けない場合は、専門のプロに頼むこともおすすめです。
関連記事:インサイトとは?
リブランディングの成功事例

市場環境や消費者ニーズの変化に対応するために、多くの企業がリブランディングに取り組んでいます。ここでは国内企業を中心に、リブランディングの具体的な成功事例をご紹介します。
- 株式会社資生堂
- 株式会社祇園辻利
- 株式会社湖池屋
- ヤンマー株式会社
- KLASS株式会社
- 株式会社MOLDINO(旧:三菱日立ツール株式会社)
- 三菱マテリアル株式会社
株式会社資生堂
資生堂は、グローバル市場での中核ブランド「SHISEIDO」の位置づけを明確にするために、リブランディングを行いました。
商品や宣伝ビジュアル、ブランドロゴを一新し、顧客との共感を生み出すための取り組みを実施。結果として、国際市場での競争力を向上できた事例です。
株式会社祇園辻利
祇園辻利は、1860年創業の老舗の宇治茶専門店です。ペットボトルのお茶が普及する時代に、改めて急須でいれるお茶の良さを伝えるリブランディングを実施。
プロジェクトの一環として、茶葉のパッケージをリニューアルしました。折り紙をモチーフとしたパッケージは和の心を伝えるデザインで、グッドデザイン賞を受賞するなどの成功を収めています。
株式会社湖池屋
湖池屋は、新社長の就任をきっかけにリブランディングを実施。「妥協なく一番おいしいポテトチップスをつくる」という原点に立ち返り、プロジェクトを始動します。リブランディングの象徴ともいえる商品が「KOIKEYA PRIDE POTATO」です。
従来のポテトチップスからは考えられないようなシンプルなパッケージが特徴で、差別化に成功しています。また、プロモーションをインパクトのある内容にすることでブランドイメージを刷新し、売上を大幅に伸ばしました。
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社は、創業100周年を機にブランドイメージの統一を目指して大規模なリブランディングを実施しました。日本では「ヤン坊マー坊」がキャラクターの農業分野の企業、ヨーロッパではエンジンメーカー。こうしたイメージがそれぞれで定着しており、認知の統一が課題となっていたといいます。
そこでアートディレクターの佐藤可士和氏を起用し、ロゴや製品デザインを刷新。グローバル市場での認知度を高めることに成功しました。
KLASS株式会社

70年以上の歴史を持つKLASS株式会社は、事業構造に対して社名や理念体系にズレが生じていたためリブランディングを実施。コンテンツによってバラバラだったロゴの表記方法を統一し、社名を「KLASS」に変更しました。
社員参加のリブランディングプロジェクトにて、CI(Corporate Identity)を再構築。新しいビジョンに基づいたブランドガイドラインを策定しました。社内外に統一されたブランドメッセージを発信することで、企業の競争力を向上できた事例です。
株式会社MOLDINO(旧:三菱日立ツール株式会社)

株式会社MOLDINOは、超硬合金・特殊鋼等による切削工具、素材等の製造販売を行う企業です。日立グループから三菱マテリアルグループへと変遷する中で、自社の強みやブランド価値を明確にするためにリブランディングを実施。
ブランドイメージを調査・分析し、ロゴやメッセージを刷新しました。リブランディングによって新しい企業文化を社内外に浸透させ、ブランドの一貫性を確立できた事例です。
三菱マテリアル株式会社

超硬製品などの製造・販売をしている三菱マテリアルは、グループ会社mctと連携しリブランディングを実施しました。
ユーザー調査の結果をもとに、ビジョン・ミッション・ブランドコンセプトを策定。それらを社内外に浸透させるためのインナーブランディング・アウターブランディング施策も展開しました。リブランディングを通して、新たなブランドイメージを確立できた事例です。
リブランディングにお悩みなら大伸社コミュニケーションデザインまで
本記事では、リブランディングについて解説しました。
リブランディングは企業のブランド価値を再定義し、市場での競争力を高めるための重要な戦略です。適切なタイミングで、慎重に計画を立てて実施し、企業の成長とビジネスの成功につなげましょう。
また、自社の価値を把握できたとしても、その価値が社内外に、正しく魅力的に伝わらなければ意味がありません。
大伸社コミュニケーションデザインでは、リブライディングの支援を行っています。ブランディング戦略にお悩みの方は、ぜひお問い合わせください。