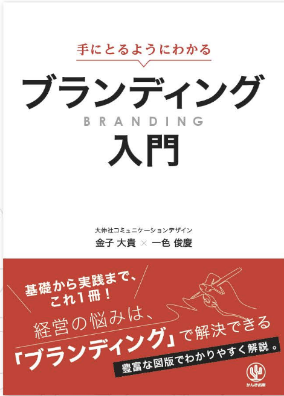採用活動において「応募者数が伸びない」「良い人材が採れない」といった悩みを抱える企業は少なくありません。従来の求人広告だけでは企業の魅力が伝わりにくいことから、重要な取り組みとして注目されているのが「採用ブランディング」です。
本記事では、採用ブランディングの基本から、取り組むメリット、具体的な進め方をまとめました。使用するチャネルの種類や参考になる成功事例なども踏まえて、初めての方でも実践できるようにわかりやすく解説します。
- 目次
採用ブランディングとは

採用ブランディングとは、企業が自社の魅力や価値観をわかりやすく伝えることで、求職者に「この会社で働きたい」と感じてもらうための取り組みです。
ここでは、採用ブランディングについて、目的や、採用広報・採用マーケティングとの違いなどを踏まえて解説します。
採用ブランディングの目的
採用ブランディングは、自社のブランドコアを伝えることで「この会社で働くことは魅力的だ」と感じてもらい、ファンになってもらうための戦略です。 採用ブランディングを行うことで、自社のブランドに共感した採用応募者の数を増やしたり、離職率を低減したりする効果が期待できます。
関連記事:ブランディングとは?意味や目的・課題別の取り組み方も紹介
採用広報・採用マーケティングとの違い
採用ブランディングと似た言葉に「採用広報」や「採用マーケティング」などがありますが、それぞれ目的や役割が異なります。
採用広報は、自社に関する情報を広く発信することで、求職者の認知度を高めることを目的としています。採用マーケティングは、求職者のニーズや行動を分析したうえで、応募を促進するための施策や導線設計に力を入れる活動です。 上記の取り組みを包括し、企業の魅力や価値を中長期的に発信していくのが「採用ブランディング」です。
採用ブランディングが注目されている背景

なぜ採用ブランディングが注目されているのか、以下のポイントに絞って背景をご紹介します。
- Z世代による企業選びの軸や価値観の多様化
- 人手不足による採用市場の競争激化
- SNSの普及
Z世代による企業選びの軸や価値観の多様化
近年、採用ブランディングが重要視される背景には、募集対象の中心となるZ世代の価値観の変化があります。
Z世代には次のような特徴があります。
- 多様性を重視している
- 環境問題に高い関心を持っている
- 「誰と働くか」を重視する
- 企業にも社会問題への取り組みを求める
企業は報酬や福利厚生のメリットを訴求するのに加えて、上記のような意向に沿える魅力も的確に伝えなければなりません。こうしたZ世代の志向と社会的な流れを背景に、企業が採用のブランド戦略を見直す重要性が高まっています。
人手不足による採用市場の競争激化
日本国内では慢性的な人手不足の影響により、企業間における人材獲得の競争が依然として続いています。特に即戦力となる優秀な人材や若手層は、業種・規模を問わず、多くの企業が人材確保にしのぎを削っている状況です。
このようななか、求人募集を出すだけでは人材は集まりません。求職者から「選ばれる企業」になるためには、採用ブランディングにより自社の魅力や価値を言語化し、ターゲット層の心に響くメッセージとして発信し、アピールすることが重要です。さらに、今後は少子高齢化による労働人口の減少により、競争はさらに激化していくと予想されます。
SNSの普及
近年のSNSの普及により、企業の情報発信がしやすくなったことも大きな要因です。
InstagramやX(旧:Twitter)、TikTok、YouTubeなどのプラットフォームを活用すれば、採用サイトだけでは伝えきれないリアルな情報を届けられます。
例えば、社員の日常や社内イベントの様子、働く人の価値観やチームの雰囲気など、現場の「空気感」や企業文化をそのまま発信できるのはSNSならではの強みです。また、リアルタイムでの発信や双方向のコミュニケーションが可能なため、求職者との距離を縮めやすいことも特徴です。
こうした特性は採用ブランディングと非常に相性が良く、Z世代を中心とした若い世代へのアプローチ手段として有効です。
採用ブランディングに取り組むメリット

ここからは、企業が採用ブランディングに取り組むメリットをご紹介します。
- ブランドコアに共感した社員を採用できる
- 採用コストを削減できる
- 従業員のエンゲージメントが向上する
- 企業の認知度が向上する
- 応募者が増加する
- 持続可能な成長の鍵となる人的資本経営に必要な戦略的採用ができる
ブランドコアに共感した社員を採用できる
採用ブランディングに取り組み、ブランディングを意識し一貫した採用活動を続けることで、自社の考え方に共感した人材が集まりやすくなります。優秀な人材を採るだけでなく、「企業が大切にしている軸=ブランドコア」に共鳴する人材を確保できるようになります。 自社の価値観に共感して入社した人材は企業文化やチームの雰囲気にも馴染みやすく、早期からの活躍が期待できます。また、入社前後でのギャップも少ないと考えられるため、離職リスクが低く、長期的に貢献してくれる人材の確保につながるでしょう。
採用コストを削減できる
採用ブランディングにより、採用コストを削減できることも大きなメリットです。
採用ブランディングに取り組むことで企業の魅力が広く浸透し、自然と「この会社で働きたい」と思う応募者が増えるようになります。こうした状態をつくれれば、求人広告や人材紹介サービスなどの高コストな採用サービスにかける費用を削減できます。
また、ブランディングを継続的に行うことで、企業に共感する“ファン”が増えれば、情報発信に対する反応率も向上するでしょう。SNSやWebサイト上のオウンドメディアといった低コストで運用できるチャネルからでも、新卒採用・中途採用問わず、十分に応募者を集められるようになる可能性があります。
従業員のエンゲージメントが向上する
採用ブランディングでは、従業員のエンゲージメントを向上させる効果も期待できます。
自社が「何のために存在し、どこを目指しているのか」が社員に伝わることで、日々の業務が組織の目的に貢献しているという実感につながります。自然と社員のモチベーションが高まり、働きがいを実感したり、自発的に行動しようとする意欲が向上したりしやすくなります。
企業の方向性が社内で共有されることで、部署間の連携やチームの一体感も強まりやすくなるでしょう。
企業の認知度が向上する
採用ブランディングでは、従業員のエンゲージメントを向上させる効果も期待できます。
SNSやオウンドメディアなどで自社の魅力を発信し続けることで、これまでは接点のなかった層にも情報が届くようになるかもしれません。
認知度が高まれば「この会社、聞いたことがある」「いい印象がある」といった心理的な安心感が生まれ、応募のハードルが下がる効果も期待できます。
応募者が増加する
応募者が増加することも、採用ブランディングに取り組む大きなメリットです。
企業のビジョンや価値観、職場の雰囲気などを的確に届けられるようになれば、求職者の興味を引きやすくなります。共感も得やすくなるでしょう。「この会社で働きたい」と感じる人が増え、応募者数の増加が期待できます。
条件のみで応募してきた人材とは異なり、理想とする人材像に近い応募者や、企業理念や価値観に共感した応募者が増えるため、自社にマッチした人材を効率よく集めるうえでも効果的です。
持続可能な成長の鍵となる人的資本経営に必要な戦略的採用ができる
企業ビジョンを叶える人材を採用することをビジョンマッチ採用といいます。
ビジョンマッチ採用は、企業の深い理解と長期的なビジョンに基づいた戦略的な採用プロセスであり、採用活動を単なる人員補充ではなく、企業と従業員の双方にとって最適なマッチングを実現するための方法です。
採用ブランディングでは、ビジョンマッチ採用に取り組むことで、持続可能な成長の鍵となる人的資本経営に必要な戦略的採用ができるようになります。
戦略的採用をするために、弊社では「 ビジョンマッチ戦略策定支援」サービスを提供しています。自社が目指すビジョンに対して、どのような人材が必要で、その人材がどのようなスキルや能力を持っているべきかを明確化し、その対象となる求職者に響くコミュニケーションを支援させて頂いております。
本サービスにご興味のある方は、企業文化への適合性を高める採用ブランディングのポイントから、具体的な施策の提案まで、採用成功に向けた包括的なガイドラインをご用意しております。以下のURLより無料でダウンロードして頂けます。
採用ブランディングに取り組むデメリット

採用ブランディングにはさまざまなメリットがありますが、取り掛かる際はデメリットも押さえておきましょう。採用ブランディングに取り組むデメリットは以下のとおりです。
- 新しい取り組みとなるため手間・時間がかかる
- 人事側がブランディングの理解を深める必要がある
- 社員を巻き込んだインナーブランディングの実施が必要になることがある
- 会社全体の取り組みが求められる
- 部門横断をして連携する必要がある
新しい取り組みとなるため手間・時間がかかる
採用ブランディングでは、自社の魅力や価値観を明確にし、適切に発信するための戦略設計やコンテンツ制作が必要です。新しい取り組みとなるため、一定の手間や時間がかかる点には注意しましょう。
また、採用ブランディングは基本的に長期的なプロジェクトなので、短期で成果を上げることが難しい場合もあります。
人事側がブランディングの理解を深める必要がある
採用ブランディングを機能させるためには、人事担当者自身がその意義や目的を深く理解していることが前提です。採用ブランディングに対する認識が浅いままだと、求職者との接点で発信がぶれて十分な効果が得られない可能性があります。また、社内での連携が難しくなる弊害もあります。
人事担当者や面接官となる社員が採用ブランディングの重要性を理解できていない場合、まずはその認識を共有するところからスタートしなければなりません。
社員を巻き込んだインナーブランディングの実施が必要になることがある
採用ブランディングは人事部門だけで完結するものではなく、実際に働く社員の理解と協力が欠かせません。
ブランドコアを社内全体に浸透させて一貫性のあるメッセージを発信するには、社員を巻き込んだインナーブランディングが必要になることもあります。
関連記事|インナーブランディングとは?
会社全体の取り組みが求められる
採用ブランディングを効果的に推進するためには、人事部門だけではなく、会社全体が一体となって取り組むことが求められます。人的資本経営を前提として、経営戦略のなかで、未来に必要な人材像(部署・部門・人物・必要スキル)を検討する必要があるからです。 しかし、実際には各部門や社員によって意識や価値観が異なることもあり、全社的な共通認識の形成や浸透には多大な労力や時間がかかります。トップダウンでの施策だけでは現場の協力を得づらく、形骸化するリスクもあるため、全社規模で自主的な取り組みを促す工夫や継続的なコミュニケーションが不可欠です。このように、採用ブランディングは一部門だけで完結しない点が大きなデメリットになり得ます。
部門横断をして連携する必要がある
採用ブランディングの推進では人事部門だけでなく、経営企画や広報、営業など多岐にわたる部門が密に連携し、情報共有や施策遂行を行う必要があります。さらに、現場の担当者からマネジメント層まで、さまざまな役職が関わって取り組まなければなりません。
しかし、部門や役職ごとに業務の優先順位や目標が異なるため、十分な連携が取れないことも多く、意思疎通の調整や合意形成に時間を要するのが実情です。大企業や事業部が多い企業ほど、縦割り意識が根強く残りやすく、全社的な巻き込みには障壁が伴いやすくなります。 そのため、部門横断の連携体制を構築することは採用ブランディング推進のデメリットとなります。
採用ブランディングの進め方

採用ブランディングの進め方を具体的にご紹介します。これから採用ブランディングに取り組もうと考えている担当者の方は、6つのステップを参考にしてみてください。
- 自社のMVVを整理する
- 採用ブランディングの目的を決める
- 求める人物像からペルソナを作る
- 発信するメッセージやコンテンツを決定する
- 採用活動を開始する
- 採用活動の検証と改善をする
1. 自社のMVVを整理する
はじめに重要となるのが、MVV(ミッション、ビジョン、バリュー)とそれに基づくブランドコアの設定です。
MVVがしっかりと設定されていない場合は、企業ブランディングも視野に入れましょう。ヒアリングや調査・ワークショップなどを通してMVVを策定するところから実施するのがおすすめです。
関連記事|ミッション・ビジョン・バリューとは?事例から作り方までご紹介
2. 採用ブランディングの目的を決める
ブランドコアを設定できたら、採用ブランディングを通じて達成したい目標を設定します。優秀な人材の確保、企業文化の浸透、離職率の低下など、具体的に定めるようにしましょう。
戦略の方向性が明瞭になり、プロジェクトをスムーズに進めやすくなります。
3. 求める人物像からペルソナを作る
次に、自社がどのような人材を求めているのかを設定します。目指す自社の姿に向けて、どのような人材であればマッチしそうかを考えることが重要です。 このフェーズで採用したい人材のペルソナを作り上げておくと、より具体的にイメージしながら進められるようになります。具体的なペルソナの情報はペルソナシートを用意して、詳細をまとめていきます。

弊社では、求職者ペルソナの設定をはじめ、実際の求職者への意識調査や現状の採用サイトに対するユーザー評価を実施することもあります。 例えば「就職活動における企業サイトの重要度は?」といった質問や、競合企業のサイトを並べ「この中から採用サイトだけを見て最も興味を持った企業はどこですか?」「その理由はなんですか?」などの質問を行うことで、求職者のインサイトを把握します。それをもとに、現状の採用サイトなど、コミュニケーション施策の改善にも反映していきます。

弊社では、内定者の保護者の方から質問をいただき、その情報をもとに「数字で見る大伸社コミュニケーションデザイン」という内容を採用パンフレットに設けました。
後述しますが、近年は内定承諾のフェーズにおいて、内定者の保護者が最終的な意思決定に影響を与えることが多くなっています。この背景から、保護者の思いにも目を向け、良い経験を創出し、エンゲージメントを高めていくことが重要だと弊社では考えています。
「御社の離職率を教えていただけますでしょうか?」「月の残業時間はどの程度でしょうか?実績値を教えてください。」など、実際に内定承諾のフェーズでいただいた質問があります。こういった質問にお応えする情報が、既存の採用サイトにはなかったため、コミュニケーション施策を改善すべく、定量情報と定性情報(社員からのリアルなコメントを掲載)をバランスよく盛り込んだコンテンツを設けました。
関連記事|ブランディングでも重要なペルソナ設定。その解像度を上げるポイントとは?
4. 発信するメッセージやコンテンツを決定する
ペルソナが設定できたら、求める人物像に響くメッセージやコンテンツを検討して作成します。「とりあえず採用サイトをリニューアルする」といった考えではなく、「ペルソナが自社のファンになり応募したいと思えるために何が必要か」を考えることが重要です。
このフェーズにおいて重要なのが、カスタマージャーニーマップです。

カスタマージャーニーマップを作成するうえで大切なのは、ペルソナの行動・ニーズをより深掘りすることです。
例えば、自社のWebサイトへの訪問にあたって、初めてWebサイトを見た時、採用候補者として訪れた2回目以降、内定承諾後に閲覧する3つの状況では、求めている情報が異なります。サイト内の回遊の仕方も変わってきます。
そこでユーザーの行動やニーズを軸にカスタマージャーニーマップを作成することが重要です。ペルソナが抱えている興味・関心をより広げたり、課題解決ができたりするメッセージ、コンテンツが何かを、行動ステージの段階ごとに考えていきましょう。加えて、ユーザー体験に沿ったWebサイトの構成、サイト内の導線を戦略的に設置することも大切です。
関連記事|ブランディングにおけるカスタマージャーニーマップの活用法
5. 採用活動を開始する
発信する内容が整理できたら、実際に採用活動を開始しましょう。
採用ブランディングにおいて特に重要となるのが、面接のフェーズです。面接官が話す内容と会社が打ち出している採用メッセージが矛盾していれば、求職者は不審に思い、内定辞退につながるかもしれません。
一方、面接官の発するメッセージに深く共感し、それまではあまり興味を持っていなかった求職者がファンとなる可能性もあります。採用ブランディングの重要性を理解し、ここまでのポイントと流れを社員がしっかりと把握したうえで採用を進めることが大切です。
また、自社のブランドコアを伝えるだけでなく、求職者がブランドコアに合っているかを見極める質問設計も重要です。例えば、自社のバリューとして「挑戦」を掲げていた場合は、求職者が今までどのような挑戦をしたのか、そして、それが自社のビジョンとマッチしているかを検証しましょう。 さらに面接でのやりとりでは「求職者からも評価をされている」という意識が必要です。実際に、面接官が高圧的な態度をとったことが求職者によってSNS上に公開され、企業の評価が著しく下がったという事例もあります。企業側の対応が、ブランドコアに沿っているかを求職者に見極められている場面として捉えることもポイントです。
6. 採用活動の検証と改善をする
採用ブランディングには終わりはありません。市場や社会情勢が移り変わることを前提に、定期的な検証・改善を繰り返す必要があります。
採用選考が終了したタイミングで次期の採用活動に向けて改善すべきポイントを洗い出し、改善方法を検討しましょう。実際の応募数やサイト内のアクセス数などの数値の他にも、説明会でのアンケートや質疑応答で集まったリアルな声をもとに改善につなげられます。
採用ブランディングを行うチャネルの種類

採用ブランディングを効果的に行うためには、チャネルを上手く活用することも重要です。以下では、採用ブランディングを行うチャネルの種類と特徴についてまとめました。
- コーポレートサイト
- SNS
- 動画
- 求人ポータルサイト
- オフラインイベント
コーポレートサイト
コーポレートサイトは、採用ブランディングの基盤となる重要なチャネルです。
企業の公式Webサイトに採用専用ページを設けることで、企業理解を深めたい求職者に直接情報を届けることができます。
仕事内容や待遇・福利厚生、社内制度など条件面の紹介に加えて、ブログや社員インタビューを通じてリアルな職場の雰囲気を伝えることも可能です。会社説明会では伝えきれない情報の発信に役立ちます。
SNS
X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、LinkedIn、WantedlyなどのSNSは、若年層の求職者にリーチしやすく、情報の拡散力が高いことが特徴です。
リアルタイムに社員の日常や企業文化を自然体で伝えられて、求職者との距離を縮めやすい点もメリットとなります。企業への共感や親近感を生みやすいチャネルです。
SNSは企画立案や制作するのに人件費は発生するものの、無料でアカウント取得や運用、情報発信ができるのも魅力です。
動画
動画は情報量が多いため、テキストや画像だけでは伝わりにくい職場の雰囲気や実際の働き方を伝えるのに効果的です。また、経営陣からのメッセージを届けるうえでも役立ちます。
社員や経営者へのインタビュー、オフィス紹介、仕事の様子などを映像で伝えることで、職場の雰囲気やカルチャーをよりリアルに感じてもらえます。YouTubeや自社のWebサイトなどで公開すれば、配信コストもかかりません。
求人ポータルサイト
リクナビやマイナビなどの求人ポータルサイトは、一般的に、広範囲の求職者にアプローチしたい場合に便利な媒体です。ただし、多くの企業が利用しているため、他社と差別化する工夫が求められます。
魅力的なキャッチコピーや写真、社員の声を活用した情報発信など、ビジュアルや文章で「自社らしさ」を伝えることがポイントです。
オフラインイベント
合同企業説明会やインターンシップ、自社開催の採用イベントなどは、求職者と実際に会話ができる貴重な機会です。
オンラインでは伝わりづらい、企業の雰囲気や想いをダイレクトに伝えられるほか、対面ならではの印象や信頼感を与えやすいこともメリットです。直接コミュニケーションを取ることで、企業理解の深まりや志望度の向上、内定者にとっては入社に向けた期待への変換にもつながります。
また、入社の意思決定において、内定者はもちろんのこと、内定者の保護者の考えや思いにも配慮することが昨今は重視されています。入社の意思確認や内定辞退を決める際に、保護者の意見が内定者に影響を及ぼすことがあるためです。
保護者のエンゲージメントを高めるブランディング活動として、パンフレットの配布やオフィスツアーの実施、プレゼントの提供などが挙げられます。
関連記事:内定者の不安を払拭し、入社への期待に変換するためにできること
採用ブランディングの成功事例

ここからは、採用ブランディングの成功事例をご紹介します。実際に採用ブランディングを進める際の参考にしてみてください。
- 株式会社メルカリ
- 日本マクドナルド株式会社
- 福島コンピューターシステム株式会社
- 株式会社NTTデータCCS
株式会社メルカリ|オウンドメディア「mercan(メルカン)」の活用
メルカリは採用ブランディングを推進する社内チーム「People Branding」を立ち上げ、オウンドメディア「mercan(メルカン)」を運営しています。
mercanでは、サービスや事業の情報ではなく、社員の声や働く姿を中心に紹介することで、求職者にリアルな企業文化を発信。「人」にフォーカスした情報発信により入社後のミスマッチを減らし、社員への共感や憧れを醸成することに成功しています。
日本マクドナルド株式会社|EVP戦略による「ハンバーガー大学」の取り組み
日本マクドナルドは、従業員への価値提案(EVP:Employee Value Proposition)を重視した採用ブランディングを展開しているのが特徴です。
その一環として、同社では専門教育機関「ハンバーガー大学」を運営しています。ハンバーガー大学では、チームビルディングやリーダーシップ、カウンセリングといったテクニカルな内容を学べます。
従業員のキャリア形成や成長を支援する環境、つまりは「従業員にとって価値のある環境」を整備することにより、従業員の定着率向上や企業へのエンゲージメント強化を実現しています。
福島コンピューターシステム株式会社|「創る未来は、想像以上 FCS!CM」の公開
福島県郡山市を拠点にICT事業を展開する福島コンピューターシステム(FCS)では、地元学生への認知向上と共感醸成を目的に、採用ブランディングCMを制作しています。給与や仕事内容ではなく、企業の想いや社会的な存在意義を前面に出した「共感採用」型のコンテンツを企画しました。
15秒のTVCMでは、音楽とビジュアルで記憶に残る仕掛けを施します。耳馴染みのない音を奏でるタブラという楽器による演奏、軽快なラップ、カラフルな歌詞の文字などです。
これらが、理解できるか否かの絶妙なスピード感で交差し、視聴者の興味を掻き立てます。目に留まりやすく耳に残る演出で、リビングでの“ながら見”を前提とした効果的なアプローチを実現しています。
CM公開後はネット上や音楽メディアで話題となり、「地方企業のCMでラップは観たことがない」と大きな反響を得ました。
株式会社NTTデータCCS|「海底から、宇宙まで。行き先はまだ決めなくていい。」採用サイトの公開
最先端のIT技術で多様なソリューションを提供するNTTデータCCSでは、SE採用数を前年比2倍に引き上げる目標を掲げ、採用サイトと動画の刷新を決断しました。夢や目標を明確に持っていない学生の「不安」に寄り添う必要性を見出し、自由な社風や多様な事業領域を生かした新たなコンセプトを定めました。
メインコンセプトは「海底から、宇宙まで。行き先はまだ決めなくていい。」です。“夢や目標がなくても構わない”という姿勢を伝えることで競合他社との差別化を図るとともに、学生の背中を押すメッセージ性を持たせています。
採用サイトと動画の公開後、「コンセプトに共感して応募した」という声が学生から多く寄せられ、エントリー数は前年比で約3倍に増加。採用者数も2倍以上を記録し、大きな成果を上げました。
採用ブランディングに関するおすすめの本

最後に、採用ブランディングに関するおすすめの本をご紹介します。採用ブランディングについて学びたいと考えている方には、以下の書籍がおすすめです。
- 知名度が低くても〝光る人材〟が集まる 採用ブランディング 完全版
- 採用ブランディングのためのデザイン&コンテンツ
- 実践・採用ブランディング
知名度が低くても〝光る人材〟が集まる 採用ブランディング 完全版
知名度の低い企業でも優秀な人材を採用・定着させられる「採用ブランディング」について解説した一冊です。
著者が1,000社以上の企業で採用活動を支援した経験をもとに、理念共感の重要性や、効果的な採用サイトの構築方法などを紹介しています。
| 書名 | 知名度が低くても〝光る人材〟が集まる 採用ブランディング 完全版 |
| 出版社 | WAVE出版 |
| 著者 | 深澤 了 |
| 出版年 | 2020年 |
採用ブランディングのためのデザイン&コンテンツ
採用ブランディングにおけるコンテンツ制作に焦点を当てたザイン事例集です。ウェブサイトや入社案内、メッセージ動画などさまざまなメディアを活用して、企業が求める人材を惹きつけるためのクリエイティブな手法が紹介されています。
巻末には、すぐに採用活動に活かせるワークシートも付録されています。
| 書名 | 採用ブランディングのためのデザイン&コンテンツ |
| 出版社 | ビー・エヌ・エヌ新社 |
| 著者 | 佐藤 タカトシ(巻頭執筆) |
| 出版年 | 2020年 |
実践・採用ブランディング
「働きたい」と思われる状況をつくり出す採用ブランディングを、どのような企業でも行えるようノウハウを解説しています。実際に100社以上の採用支援を行った著者の経験をもとに、求職者に企業の魅力を伝えるための具体的な方法がまとめられています。
リクルート、ソフトバンク、サイバーエージェントなどの事例を通じて、規模や知名度に関係なく選ばれる企業になるための戦略が解説された良書です。
| 書名 | 実践・採用ブランディング |
| 出版社 | クロスメディア・パブリッシング |
| 著者 | 佐藤 タカトシ |
| 出版年 | 2018年 |
採用ブランディングに関するご相談は大伸社コミュニケーションデザインまで
本記事では、採用ブランディングについて詳しくご紹介しました。
採用ブランディングにはさまざまなメリットがあり、企業の採用活動を行ううえでとても大切な取り組みです。しかし、自社にノウハウのない状態でブランディングの確立を成功させることは難しいものです。
採用ブランディングを実施する際は、プロのアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。ぜひ、株式会社大伸社コミュニケーションデザインにご相談ください。
弊社は、以下を通じて、クライアントのビジネスを支援しています。
- トータルなコミュニケーションデザインの提供
- ユーザーインサイトの重視
- クリエイティブなチーム
- 先進的なVR・AR技術の活用
- インナーブランディングの実施
これらの強みを活かし、企業のブランド価値を高めるための効果的な戦略を展開しています。
また、御社の顧客、御社社員のインサイトを把握し、思いをくみ取ることを大切にしています。御社のコアをつくるブランディングプロジェクトを、ブランドコアの策定〜浸透施策の検討まで。コンサルティングだけでなく、施策の実現まで伴走します。ぜひ、以下より詳細をご覧ください。
3つの領域から、企業・プロダクトのブランディング支援を。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

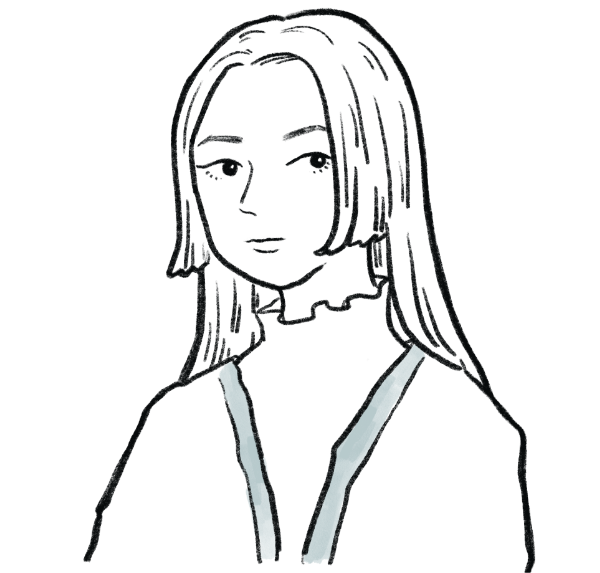

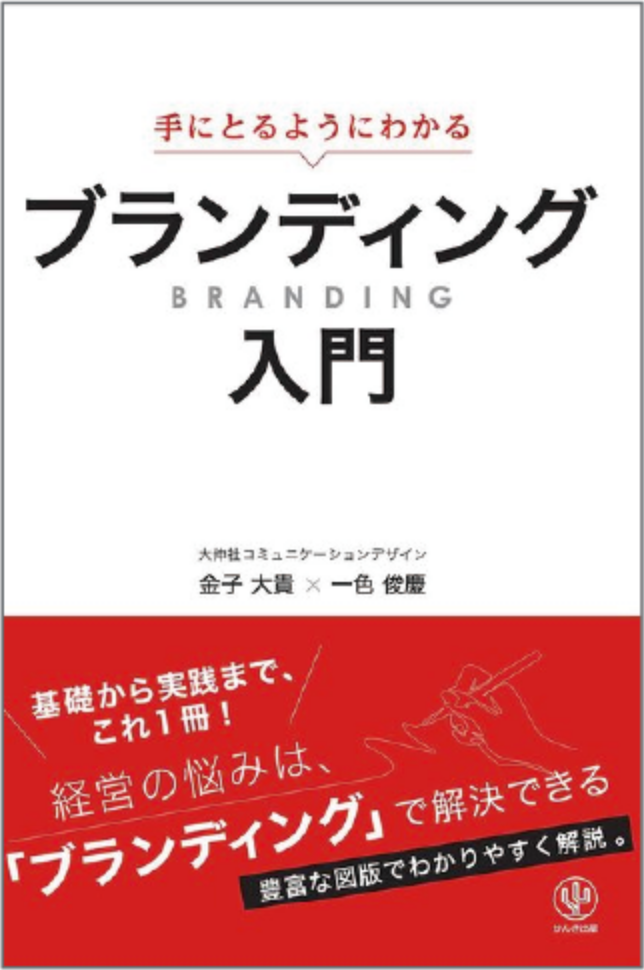 株式会社 大伸社コミュニケーションデザイン チーフ ブランディングディレクター コピーライターとして、広告・宣伝のクリエイティブ開発の経験を経て、ブランディングに特化したプランニング・コンサルティングを担う現職へ。大手上場企業から中小企業まで、企業のリブランディングプロジェクト、新製品のコンセプト開発、ブランド浸透戦略立案などの幅広い業種業態でのブランディング支援を実施。
株式会社 大伸社コミュニケーションデザイン チーフ ブランディングディレクター コピーライターとして、広告・宣伝のクリエイティブ開発の経験を経て、ブランディングに特化したプランニング・コンサルティングを担う現職へ。大手上場企業から中小企業まで、企業のリブランディングプロジェクト、新製品のコンセプト開発、ブランド浸透戦略立案などの幅広い業種業態でのブランディング支援を実施。