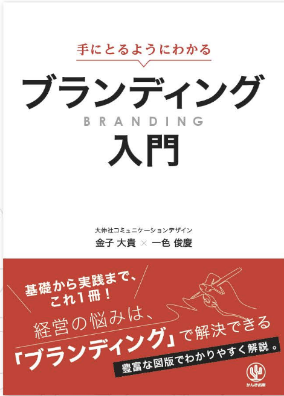市場環境がめまぐるしく変化する中で、「自社の魅力がうまく伝わらない」「他社と差別化できない」といった課題を感じている企業は少なくありません。こうした悩みに応えるのが、企業の価値や姿勢を明確に打ち出す「ブランディング戦略」です。
本記事では、ブランディング戦略の基本から、戦略を立てる際のポイント、実行・改善の進め方までをまとめました。後半では、成功・失敗事例も交えてわかりやすく解説します。これからブランディングに取り組む方や、戦略を見直したい方は参考にしてください。
- 目次
ブランディング戦略とは

まずブランディングとは、「ブランド = 見聞きした瞬間、頭に浮かぶ独自のイメージ」を形成し、確立することです。
ブランディング戦略とは、「ブランディングを始める前に自社の課題を明確にし、どう解決するかを整理した上で、戦略を立てること」です。そのため、詳しくは後述しますが、ブランディングの戦略の観点は企業の状態によって異なります。
ブランディングとの違い
ブランディングとは「見聞きした瞬間、頭に浮かぶ独自のイメージを確立するための取り組み」です。
一方、ブランディング戦略は、ブランディングを効果的に進めるための具体的な計画や方法論のことを指します。
ブランディングが「ブランドを確立するための取り組み全般」を指すのに対し、ブランディング戦略は「どう実現するか」に焦点を充てているという違いがあります。
関連記事:ブランディングとは?意味や目的・課題別の取り組み方も紹介
マーケティング戦略との違い
マーケティング戦略とは、「誰に・何を・どう届けるか」を計画し、商品やサービスを売るための仕組みを整える戦略です。マーケティング戦略を立てるために、自社や競合他社、市場や顧客ニーズの調査・分析、ターゲット・ペルソナの設計などを実施していきます。
マーケティング戦略の土台となるのがブランディング戦略です。ブランドの価値が明確になるほど、マーケティングの効果も高まります。
関連記事:ブランディングとマーケティングの違いとは?関係性や成功事例を紹介
ブランディング戦略の重要性

では、なぜ企業経営においてブランディング戦略が必要なのでしょうか。ここでは、ブランディング戦略の重要性について詳しく見てみましょう。
- 顧客視点で考えることが顧客ロイヤリティを高める
- ユーザーとの約束を実現していくための土台づくりに欠かせない
顧客視点で考えることが顧客ロイヤリティを高める
ブランドは企業が決めるものではなく、顧客の頭の中に形成されるものです。だからこそ、ブランディング戦略を通して、顕在的もしくは潜在的に「顧客がどのような価値を求めているか」「理想とするブランド像は何か」といった視点を持つことが重要です。
顧客視点で考え、共感を得られる体験やメッセージを提供することで、ブランドへの信頼がより高まります。顧客ロイヤリティの向上にもつながるでしょう。
ユーザーとの約束を実現していくための土台づくりに欠かせない
近年注目されている「パーパス経営」とは、企業の存在意義を軸に経営を行う考え方です。この考え方が広まったのは、2018年、ブラックロック社のCEOが年次書簡で発信したことがきっかけと言われています。
日本では名和高司氏が、21世紀は資本経営ではなく「志本経営」の時代であるとし、「志」すなわち未来への約束の重要性を説示しました。企業がユーザーにどのような約束をして、それがどれだけ共感されているかが、ブランドの価値を左右するとされています。
「ユーザーに何で期待されたいか」「どのような人を救いたいと思っているのか」「どのようなことで社会を良くしたいのか」。こうした強い志があるかどうかが、支持されるか否かの分かれ目になってきています。しっかりとした土台を作るためにも、ブランディング戦略は欠かせません。
ブランディング戦略のメリット

続いて、ブランディングを行うメリットを見てみましょう。以下の項目ごとに詳しく解説します。
- 認知度が向上する
- 他社と差別化できる
- マーケティングコストが下がる
- ブランドロイヤリティが向上する
- 優秀な人材が集まりやすくなる
1. 認知度が向上する
ブランディング戦略の大きなメリットは、認知度が向上することです。ブランディング戦略によって、ロゴやデザイン、メッセージなどを一貫して発信するようになれば、消費者の記憶に残りやすくなります。
「あの商品はこのブランドのものだ」とすぐに連想してもらえる状態をつくることで知名度が高まります。ブランド力のある商品・サービスは自然と選ばれる機会も増えるでしょう。
2. 他社と差別化できる
ブランドとしての世界観やストーリーで差別化することで、他社と違う形で魅力を伝えられるようになります。
「このブランドの考え方が好き」「この世界観に共感できる」と顧客に感じてもらうことで、価格や機能以上の理由で選定されるようになります。価格競争に巻き込まれにくくなり、業界において独自性を確立できるでしょう。
3. マーケティングコストが下がる
ブランドが認知されて信頼されるようになると、広告に頼らずとも自然と、自社商品・サービスが選ばれるようになります。
いわゆる「指名買い」が増えることで、都度新たなプロモーションや、マスメディアを活用したCMを行わなくても売上につながることが期待できます。
広告費や販促費などのマーケティングコストを抑えつつ、効率的な集客・販売が可能となるでしょう。
4. ブランドロイヤリティが向上する
ブランディング戦略によって信頼関係が築かれると、顧客側でのリピート購入や口コミ投稿、商品紹介などの行動が増えていきます。一度選ばれただけで終わらず、「また買いたい」「誰かに勧めたい」と思ってもらえる状態は、安定した中長期的な収益をもたらします。
長期的に応援してくれるロイヤリティの高い顧客は、企業という組織にとって大きな資産となるでしょう。
5. 優秀な人材が集まりやすくなる
魅力的なブランディング戦略は、顧客だけでなく求職者にも影響を与えます。MVV(※)が明確で、外から見ても共感できるブランド・企業であれば、「ここで働きたい」と思う人材が集まりやすくなります。
会社説明会やインターンシップ、オウンドメディア、求人サイトなどで一貫したコンセプトのもと、情報を発信することで、求職者や採用候補者の共感を得やすくなるためです。採用活動がスムーズになるだけでなく、理想の人材像や企業文化にマッチした人材が集まることで、社員の入社後の定着率や、成長力の向上も期待できるでしょう。
企業のミッションやビジョンに社員が共感することで、自身の役割を理解し、それに誇りを抱いて働きがい、仕事への意欲をもって業務に取り組むようになるためです。なお、MVVを社内に浸透させる取り組みをインナーブランディングと呼びます。詳細は「インナーブランディングとは?」をご覧ください。
このようにブランディング戦略は、人材を計画的・効果的に獲得していく採用戦略にも役立ちます。
(※)MVV:ミッション(Mission)、ビジョン(Vision)、バリュー(Value)を指す。企業経営の核となる3つの重要な要素。
関連記事:ミッション・ビジョン・バリューとは?事例から作り方までご紹介
ブランディング戦略の種類

ブランディング戦略と一口に言っても、目的や対象によって様々な種類があります。以下では、主なブランディング戦略の種類をご紹介します。
- サステナブルブランディング戦略
- サービスブランディング戦略
- 企業ブランディング戦略
サステナブルブランディング戦略
サステナブルブランディング戦略とは、企業が環境問題や社会課題に取り組む姿勢をブランディングとして打ち出す戦略です。
たとえば脱炭素や地域貢献、フェアトレードなどへの取り組みを可視化し、顧客からの共感や信頼を目的に発信します。サステナブルへの取り組みを企業理念の一環として掲げることで、価値観に共鳴する消費者との長期的な関係構築が期待できます。
サービスブランディング戦略
商品やサービスの魅力を明確にし、WebサイトやSNS、店頭などあらゆるチャネルで発信するブランディング戦略です。
サービスブランディング戦略では、単に機能を紹介するだけには止まりません。商品やサービスが持つ価値や背景、ブランドのストーリーを丁寧に伝えることでファン化を促し、顧客の共感や信頼を獲得します。
企業ブランディング戦略
企業ブランディング戦略とは、企業の価値・イメージを向上させることで、競合他社との差別化を図る戦略です。
広報活動やPR施策を通じて企業のMVVを外部に発信し、投資家や求職者、取引先など多様なステークホルダーにポジティブな印象を与えます。製品単体ではなく、企業そのものへの信頼を醸成することで、他社との差別化や長期的な企業価値の向上が期待できます。
ブランディング戦略の立て方と手順

以下では、ブランディング戦略の立て方と手順をご紹介します。
- プロジェクトの設計
- 自社・競合・顧客・社会の理解
- ブランドコアの定義
- 具体化と実行
- 効果検証と改善
1. プロジェクトの設計
はじめにプロジェクトの設計を行い、下記を明確にします。ブランディング戦略で効果的なアプローチを検討するには、的確なプロジェクトの設計が欠かせません。
- ブランディング・プロジェクトの目的 / ゴール
- ブランディングにより解決すべき課題
- ブランディング・プロジェクトの進め方
ブランディング・プロジェクトの目的 / ゴール策定
まずは、ブランディング・プロジェクトの目的とゴールを策定します。
「ブランドを通じて何を実現したいのか」を明確にしましょう。たとえば、認知度を上げたい、顧客ロイヤリティを高めたい、新卒採用・中途採用で採用力を強化して内定率・内定承諾率を上げたい、魅力的な職場環境づくりをして離職率を低下させたいなど、事業目標へとつながる具体的なゴールを設定します。
ブランディングにより解決すべき課題の抽出
ブランディングにより解決すべき課題を抽出しましょう。現状の課題を洗い出し、「ブランドがなぜうまく伝わっていないのか」を把握します。たとえば「メッセージの一貫性がない」「顧客との接点が弱い」「他社との差別化ができていない」といった具合です。
ブランディング・プロジェクトの進め方の決定
プロジェクトの体制や進行方法を決めます。社内外のメンバー構成、ステップ(調査・戦略設計・施策の実行・改善)、スケジュール、レビュー体制などを設計し、着実に進めるための土台を作りましょう。
プロジェクトの体制を決定し、どのようなメンバーで実施するのかを考えます。キックオフミーティングも実施するとスムーズです。
2. 自社・競合・顧客・社会の理解
キックオフミーティングを行いプロジェクト設計が完了したら、次は現状理解に移ります。現状理解では、「自社」「顧客」「社会」「競合」の4つの視点から自社らしさのヒントを得ていきましょう。
理想のブランドの姿として、まず自社のありたい姿と、顧客からの期待が重なる部分がブランドコアの候補になります。その上で、競合が提供していない独自のものが理想のポジショニングとなります。そのひとつの重なる点を目指し、自社、顧客、従業員、社会環境および競合他社について深く知る必要があるのです。
自社の立ち位置を把握し、改善につなげるためにおすすめなのが「ブランディングコンパス」です。無料診断は3分で完了するので、ぜひお試しください。
3. ブランドコアの定義
現状理解を十分に行ったら、次はブランドコアの定義をする段階です。前ステップまでに行った現状調査をもとに、自社ブランドの「核」となる価値や考え方、コンセプト = ブランドコアを明確にしましょう。
企業がどのような存在でありたいのか、どのような価値を顧客に提供するのかを言語化するプロセスです。ブランドコアは社内の意思決定や社員の行動の基準にもなるため、全社的に共有し、浸透させる準備が重要です。
4. 具体化と実行
ブランドのコアが定義されたら、いよいよ発信・浸透、すなわち実践的なブランドの展開を行っていきます。ブランドの展開については、社内向けの「インナー・ブランディング」と社外向けの「アウター・ブランディング」の2種類があります。
まずはインナー・ブランディングを進めていき、ある程度社内に浸透してからアウター・ブランディングを始めるという段取りがセオリーです。
関連記事:インナーブランディングとは?
5. 効果検証と改善
実際にブランディングの取り組みを始めたら、一定期間が経過した頃に成果を測定するようにしましょう。ブランディングを推進する上での指標として役立ちます。
手法としては、ユーザーリサーチが主となります。こうした数値をもとに毎年、定点観測を行いながら、どういった取り組みが評価されているか調査しましょう。より強めるべき取り組みは何かを再考し、新たなアウター / インナー・ブランディングの取り組みを推進していくことが重要です。
ブランディング戦略で現状理解を行うためのフレームワーク・方法

ここからは、ブランディング戦略で現状理解を行うためのフレームワーク・方法について解説します。
- 自社のありたい姿の探索
- PEST分析・PESTLE分析…自社を取り巻く外部環境の理解
- クロスSWOT分析…自社の強みと機会の理解
- 3C分析…競合と比べた自社の強みや弱みの理解
2〜4はマーケティング領域でも有名なフレームワークであり、精度を追求すればどこまでも詳細に調べることができます。しかし、あくまでも「自社を客観的に理解する」ことが目的ですので、可能な限りの実施で構いません。
ブランディングの領域において特に大切なのは「1. 自社のありたい姿を探索する」になります。というのも、2〜4の分析を自分たちで行う際、どうしても自分たちの視点からの分析になりがちであり、実態とズレが生じていることがあるからです。

自社のありたい姿の探索
自社のありたい姿と言っても、簡単に一言で言語化するのは難しいものです。そのヒントとなる項目は以下の通り。以下の観点から、自社らしさにつながる要素を抽出していくことがポイントです。
- 会社の存在意義として捉えているもの(パーパス)
- 会社としてありたい姿(ミッション/ビジョン)
- 会社として大切にしている価値観/ DNA(バリュー)
- 会社としての強み/他社との違い
- 顧客から見た現状の会社のイメージ/社員から見た社風
会社の存在意義として捉えているもの(パーパス)

近年ではMVVの根底にある、パーパス(Purpose)という考え方も認知され始めています。パーパスの役割は、「そのブランドがなぜ存在するのか?」という存在理由【Why】に該当します。
パーパスが問われるようになったことは、社会環境や自然環境が大きく変化しており、自社の利益だけを追求することが場合によっては批判されるようになったことにあります。また、自社の発展も自力だけでは難しく、多くのステークホルダーと共創しながら共存共栄を図るほうが現実的な道筋となってきていることも要因です。
会社としてありたい姿(ミッション / ビジョン)

ビジョンとはブランドが考える夢であり、将来の自社と社会の理想像です。「自社がどのような未来を作りたいのか?」をベースに考えましょう。ビジョンを議論・作成するワークショップで特に重要なのが、否定をしないことです。どのような未来を実現できたらよいか、従業員が喜ぶか、子どものような視点で考えることが効果的です。
ミッションの設定では、「ビジョンを実現するために、果たすべき使命は何か?」について議論しましょう。「企業として何を果たさなければならないのか?」「どのような役割を果たす必要があるのか?」を話し合います。
会社として大切にしている価値観 / DNA(バリュー)
バリューとは、「ミッション・ビジョン実現のために大切にすべき価値観」のことです。日々の具体的な行動の際に参考とする、価値観としてのキーワードを抽出し策定しましょう。バリューは複数のキーワードからなることも多くあります。
会社としての強み / 他社との違い
自社の強みを把握することは、ブランドの差別化につながる重要なポイントです。
単に製品スペックや価格だけでなく、「なぜ顧客に選ばれているのか」という根本的な理由に着目してリサーチしましょう。競合他社との違いを客観的に比較し、「自社ならでは」と言える価値を見つけることがブランドの軸になり得ます。
市場調査やインタビュー形式の顧客リサーチなどを通じて、データや事実に基づいた強みを言語化することが大切です。
顧客から見た現状の会社のイメージ / 社員から見た社風
ブランディング戦略では、企業が伝えたいイメージと、顧客や社員が実際に感じているイメージとの一致も重要です。
顧客からの評価は、サービスや商品を通じた体験で形成されています。「信頼できる」「親しみやすい」「価格が安い」など実際の経験を通して抱いた印象が、ブランドイメージに影響します。
一方、社員から見た社風は、働きやすさや理念への共感度、日々の業務スタイルから感じる「会社らしさ」に表れます。社内と社外でブランドに対する認識が食い違っていないかを見直しましょう。
顧客から見た現状の会社のイメージと会社の実態にズレがないかを確認し、必要に応じて調整することがブランドの一貫性と信頼構築に欠かせません。
PEST分析

自社のあるべき姿を考える際には、社会からの要請を理解することが欠かせません。その第一歩として自社を取り巻く環境を把握・理解することが必要であり、それを可能とするフレームワークが「PEST分析」です。
PEST分析 とは、Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の頭文字を取った言葉。自社を取り巻く外部環境について、この4つの観点から理解しようとするものです。
詳細な観点は図に示した通りです。自社のブランドに何が影響するのか、どんな変化が求められているのか?の視点を得ることが大切です。
PESTLE分析
PESTLE分析とは、「PEST分析」に加えて環境やリスク分析を行うためのフレームワークです。以下のマクロ環境の頭文字を取ったもので、PEST分析よりもさらに高度な環境分析を行えるのが特徴です。
- 政治的要因(Political)
- 経済的要因(Economic)
- 社会的要因(Sociological)
- 技術的要因(Technological)
- 法的要因(Legal)
- 環境的要因(Environmental)
クロスSWOT分析

「SWOT分析」とは、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の頭文字を取った言葉。強み・弱み・機会・脅威の4 つを漏れなく挙げることで自社の現状を分析する手法です。
このうち強みと弱みはその事業自身が持つもので「内部環境」と呼ばれます。また機会と脅威は社外から与えられるもので「外部環境」と呼ばれます。
たとえば、前項のPEST分析のうちP、E、S(政治、経済、社会)は外部環境の要素になり得ます。T(技術)は社内で持っているものは内部環境になり得ますし、そうでなくこれから普及していくような技術は外部環境に当たります。SWOT分析を列挙するだけでも考察の材料にはなりますが、戦略や方針にはなりません。
そこで内部環境と外部環境をかけ合わせて分析し、自社の戦略や方針を考察するフレームワークとして、「クロスSWOT 分析」が登場しました。
内部環境も外部環境も2つずつありますので、かけ合わせると4つの考える観点が生まれます。
3C分析

市場を理解するためのフレームワークとして代表的なものが「3C分析」です。3Cとは、Customer(顧客・市場)、Company(自社)、Competitor(競合)の3つのCを意味しています。
市場にはこの3つの登場人物がおり、それぞれを理解していないと市場を理解していることにはならないという考え方に基づいています。
また、さらに詳しく調べるのなら、「4C分析」も効果的です。4Cとは顧客の購買意思決定に影響を与える4つの要素「顧客価値(Customer Value)」「価格(Cost)」「利便性(Convenience)」「コミュニケーション(Communication)」の4つのCを意味しています。4C分析では、その4つを顧客側の視点で捉え、市場調査を行い、各項目の分析を行っていきます。
ブランディング戦略を立てるポイント

ブランディングに取り組もうした際、すべての企業が同一のプロセスや内容で行えるわけではありません。企業の状態によって、ブランディングの戦略の観点は異なります。
以下ではブランディング戦略を立てるポイントについて、企業のフェーズ別に解説します。
初めてブランディングを行う企業
先に触れた通り、ブランディング戦略のフェーズは以下のように分かれています。
- プロジェクトの設計
- 自社・競合・顧客・社会の理解
- ブランドコアの定義
- 具体化と実行
- 効果検証と改善
ブランドコアが明確でなく、ビジョンや志が見える化されていないのであれば、「1. プロジェクトの設計」から取り組みましょう。
ブランドの定義はされているが、社内に浸透ができていない企業
「社内・社外浸透が不十分である」といったように、現場の課題が明確な場合は必ずしもブランドの定義から行う必要はありません。
ブランドコアの定義が的確であることを確認した上で、「4. 具体化と実行」に着手しましょう。特に、インナーブランディングの見直しを行うことが重要です。
社外へ適切に伝える内容・手段が決まっていない企業
社内への浸透はできているものの、社外へ適切に伝える内容・手段が決まっていないというケースもあるでしょう。そういった場合は、「4. 具体化と実行」のなかでもアウターブランディングが必要となります。
ブランディングを始める前にどのような課題があり、どのプロセスを行うことで課題解決ができるのか見定めて戦略を作ることが重要です。
ブランディング戦略の成功事例

ここからは、ブランディング戦略の成功事例をご紹介します。大手企業の実績をまとめたので、これからブランディング戦略に取り組む方は参考にしてください。
- ターゲットを究極に絞ったマツダのブランディング「2%戦略」
- 熱狂的なファンを生み出すスノーピークのブランディング戦略
ターゲットを究極に絞ったマツダのブランディング「2%戦略」
1990年代前半、マツダはブランドを増やし販売店ごとに取り扱いブランドを分ける「多チャンネル化」を実施しました。しかしこの戦略は振るわず、販売台数は減少しました。
対策として値引き販売の施策を実施しますが、新車の価格が安くなったことで下取り価格の大幅な値崩れが起こってしまいます。顧客はマツダに下取ってもらうしかなく、次の自動車もマツダでの購入を強いられる負のスパイラル、「マツダ地獄」に陥ってしましました。
そこでマツダはこの状況を打開しようと新たに「2%戦略」を行いました。これは当時マツダの世界シェアが2%程度であったのに対し、既存のファンに強く共感してもらえる自動車、ブランドを作っていこうという指針です。
具体的な内容は、「新型開発前に世界から5人の熱狂的なファンに意見を聞く」というものです。メーカーが製品開発のために行うヒアリングであれば、通常は数千人にも及ぶサンプルを対象とした定量的なアンケート調査や定性的なインタビューを行います。しかしマツダはこの手法を取らず、5人の熱狂的なファンに綿密なヒアリングを実施したのです。
2%のファンから共感を得るために行ったこの取り組みは大成功し、現在もマツダの主力製品となっているデザインと機能性に優れた「アテンザ」セダンが生まれました。
熱狂的なファンを生み出すスノーピークのブランディング戦略
キャンプ用品メーカーのスノーピークは、1998年にオートキャンプにおけるライフスタイルの原型を世界で初めて提唱したブランドです。「SUV(スポーツ・ユーティリティー・ビーグル)を走らせ、自然の中で豊かな時間を過ごすためにキャンプをする」という新たなスタイルを提案してきました。
アウトドア業界は1993年をピークに2009年までは市場縮小の一途を辿っていたにも関わらず、増収増益を続け、成功し続けています。これは「スノーピーカー」という熱狂的なファンがいたからです。この熱狂的なファンを作るために、スノーピークは圧倒的に高い商品力と、顧客との関係づくりに力を入れてきました。
スノーピークは全社員が大のアウトドア好きで、採用の際にもキャンプ愛好家しか採用しないそうです。そうした人たちが商品を開発しているため、当然のように顧客の目線で考えることができ、質の高い製品が生み出されるのです。
ブランドと顧客との関係性の近さも特徴的です。スノーピークの社員と既存顧客が一緒にキャンプを楽しむ「スノーピークウェイ」というイベントがその代表的な例です。メインのイベント「焚き火トーク」では、アウトドアの楽しみ方や製品について自由に会話をすることで既存顧客との距離を縮めています。ユーザーの本音をもとに製品の改良につなげるなど、様々なメリットがあるのです。
このような取り組みが成功の鍵となり、スノーピークに熱狂的なファンが存在し続けています。
ブランディング戦略の失敗事例

実際にブランディング戦略に失敗してしまった企業も多く存在します。続いては、ブランディング戦略の失敗事例にどのようなものがあるのかをご紹介します。
- 自社視点でブランドコアを決定した大塚家具
- パッケージの変更で売上減少を引き起こしたトロピカーナ
自社視点でブランドコアを決定した大塚家具
大塚家具はもともと会員制・高級路線で「お得意様扱い」に価値を見出す顧客から支持されていました。しかし2009年、長女の久美子氏が社長に就任し、「気軽に入れる中価格帯の家具店」への転換を図ります。
来客数と業績は一時的に回復したものの、最終的にはニトリやIKEAと比較されるようになり、本来のポジショニングを失ってしまいます。「従来の大塚家具よりは安いが、ニトリと比べたらかなり高い」という印象を与えてしまったのです。
久美子社長は顧客に喜んでもらえると自分なりに考え、路線変更に踏み切りました。しかし、競合に合わせた路線変更は、自社の本来の強みを曖昧にしてしまうリスクを伴います。顧客視点とは、顧客が喜ぶことを想像することではありません。「顧客が、顧客の頭の中で本当に期待する価値」を見出し、その期待に応えることがブランディングであり戦略なのです。
パッケージの変更で売上減少を引き起こしたトロピカーナ
トロピカーナ(トロピカーナ・プロダクツ社)は、人気商品のオレンジジュースで知られる企業です。みずみずしい果物にストローが刺さったパッケージが有名です。
トロピカーナは2008年より、現代的な外観にするため5,000万ドル以上の費用をかけてパッケージを大幅に変更しました。新しいデザインでは見慣れたオレンジの果実がなくなり、グラスに入ったオレンジジュースになったのです。ロゴも、従来のクラシックなフォントからよりミニマムなフォントへ変更されました。
しかし、このリブランディングから2ヶ月、トロピカーナの売上は20%にあたる約3,000万ドルの減少となったのです。わずか2ヶ月でトロピカーナは従来のデザインに戻すことを発表しました。
原因は、トロピカーナが今まで慣れ親しまれてきたクラシックなデザインを過小評価していたことにあります。「モダンであると思われたい」という気持ちから顧客目線が疎かになり、ファンを置き去りにするようなブランディングになったのです。 ブランドとは、顧客が頭の中でイメージするものです。そのイメージから大きく変わってしまうようなブランディング戦略になっていないかを十分確認し、取り組むようにしましょう。
ブランディング戦略なら大伸社コミュニケーションデザインまでご相談を
本記事ではブランディング戦略について、具体的な方法や手順、着目すべきポイントなどを詳しく説明しました。ブランディングに取り組むにあたって行うことはとても多く、一つひとつのステップが欠かせないものとなります。
弊社は、ブランド策定・インナーブランディング・アウターブランディングの3つの領域から企業・プロダクトのブランディング支援を行っている企業です。
ブランディング戦略に行き詰まっている、具体的な問題を抱えているなどでお困りの場合は、ぜひ弊社までご相談ください。貴社への最適なソリューションをご提案し、課題解決に向けたサポートをさせて頂きます。
【参考文献】
『手にとるようにわかる ブランディング入門』(金子大貴著、 一色俊慶著)
MarketingDriven マケドリ/【業界別事例あり】PEST分析とは?やり方も解説します!
https://the-marke.com/media/marketing-pest/#index_id13
Keywordmap ACDEMY/SWOT分析とは?事例から方法やコツ、注意点を解説
https://keywordmap.jp/academy/swot/#SWOT-2
THE OWNER/3C分析とは?6つの事例から学ぶ進め方のコツや注意
https://the-owner.jp/archives/2688
BISCUIT 「3分」で読めるビジネスのヒント/4C分析のフレームワークをスターバックスを事例に解説!
https://www.biscuit-online.com/marketing/354
リコーのマーケティング支援:5F(ファイブフォース)分析とは?
https://drm.ricoh.jp/lab/glossary/g00035.html
ferret マーケターのよりどころ/5フォース分析とは?やり方や注意点、大手企業の事例を解説
https://ferret-plus.com/73992#p24
デービッド・A・アーカー(David.A.Aaker)「Managing Brand Equity」
関西学院大学レポート ブランド研究における近年の展開ー価値と関係性の問題を中心にー
https://core.ac.uk/download/pdf/143635907.pdf

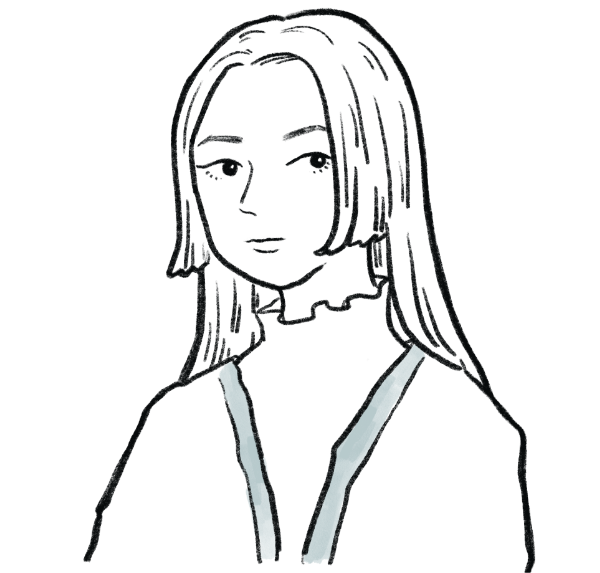

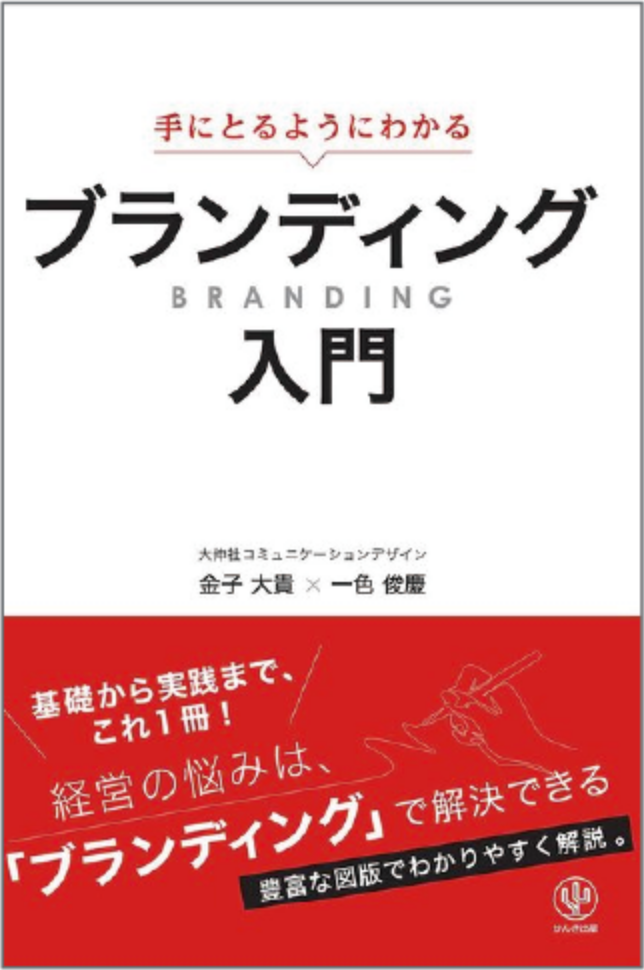 株式会社 大伸社コミュニケーションデザイン チーフ ブランディングディレクター コピーライターとして、広告・宣伝のクリエイティブ開発の経験を経て、ブランディングに特化したプランニング・コンサルティングを担う現職へ。大手上場企業から中小企業まで、企業のリブランディングプロジェクト、新製品のコンセプト開発、ブランド浸透戦略立案などの幅広い業種業態でのブランディング支援を実施。
株式会社 大伸社コミュニケーションデザイン チーフ ブランディングディレクター コピーライターとして、広告・宣伝のクリエイティブ開発の経験を経て、ブランディングに特化したプランニング・コンサルティングを担う現職へ。大手上場企業から中小企業まで、企業のリブランディングプロジェクト、新製品のコンセプト開発、ブランド浸透戦略立案などの幅広い業種業態でのブランディング支援を実施。