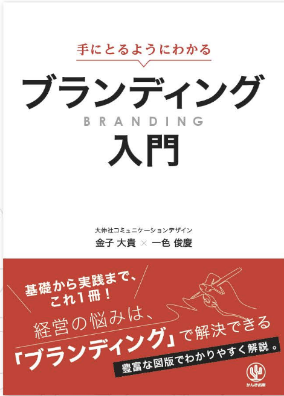企業や商品の印象を左右するロゴは、ブランドの象徴です。
しかし、ブランディングにおいてロゴが重要だと理解していても、以下のような疑問や課題を抱えている方は多いのではないでしょうか。
「何から始めればよいかわからない」
「代理店の作成したロゴやネーミングが浸透しない」
「ただ作るのではなく、皆に愛されるロゴにしたい」
本記事では、ブランディングにおけるロゴの役割や求められる条件、そして愛されるブランドの象徴となるロゴを作るためのステップについてまとめました。
後半では、ブランドに定着し、長く愛されるロゴを生み出すためのポイントや、実際の成功事例も紹介します。ロゴを通じてブランドを育てていきたい方は、ぜひ参考にしてください。
- 目次
ブランディングにおけるロゴとは?

企業や商品の印象を左右するロゴは、ブランド認識を強化するための重要なツールです。
しかし、ロゴを作ること=ブランディングではありません。ロゴ制作はあくまでブランディングの一部であり、ブランディングの目的ではありません。「ロゴさえ作ればブランディングは完了」と誤解されがちですが、形だけのロゴ制作に終始するようなことは避けるようにしましょう。
ロゴはブランド認識を強化するための重要なツール
冒頭の通り、ロゴはブランド認識を強化するための重要なツールです。
しかし、ロゴは単なるデザインではなく、ブランドの象徴として企業の理念や価値を可視化する役割を持ちます。
では、なぜ愛されるロゴが生まれるのでしょうか。それは作り方に理由があります。
ロゴを作ること自体を目的とせず、企業や製品の強み・弱み、将来の理想像、そこに込めたい想いを定義し、関係者がその考えを共有すること。さらに、自分以外の誰かの視点や感覚も尊重しながら形に落とし込んでいく、このプロセスこそがブランディングです。
プロセスが薄いロゴは形骸化し、愛されにくいものとなります。 一方で、多くの思いを受け止め、集約されたロゴは、長年にわたり人々に支持されるブランドの象徴となります。
強いブランドでは、ロゴを見ただけでブランドのコアや価値観が自然と想起されるように設計されています。それは偶然ではなく、丁寧なプロセスを積み重ねた結果なのです。
効果的なロゴ制作は「作り方」がポイント
なぜ魅力的なロゴを制作できるのでしょうか。その理由は作り方にあります。ロゴ制作を単なるゴールにせず、まずは企業や製品の良さや強み、競合と比べた弱み、そして未来像やなりたい姿といった曖昧な要素を言葉で定義します。次に、その考えを関係者全員で共有し、自分以外の誰かの思いや価値観も尊重しながら、「感覚」をひとつの形へとまとめ上げていきます。
このプロセスこそがブランディングであり、ロゴはその結果にすぎません。形だけを整えても、プロセスが浅ければロゴは愛されず、やがて形骸化します。一方で、多くの思いを受け止め、丁寧に集約された「濃い思い」が込められたロゴは、長い年月を経ても愛され続けます。
あるブランドの立ち上げ事例では、次のような要素がロゴを戦略的に強化する鍵となりました。
- 共通認識の形成
事業や理念を一目で理解させる象徴として機能させる。 - 参加型の開発
関係者を巻き込み、愛着と当事者意識を育む。 - 世界観の明確化
キーワードを抽出し、言葉とデザインを一致させる。 - 象徴性と一貫性
見ただけでブランドを想起できる形と色を設計する。 - 活用の広がり
あらゆる接点で使い、認知度と愛着を高める。
ロゴは単なる視覚的マークではなく、ブランドの価値や世界観を言語化し、関係者の思いを集約し、社内外の共通認識を形にする戦略的ツールです。効果的なロゴは偶然ではなく、緻密で参加型のプロセスから生まれます。作り方が重要であると理解しておきましょう。
参考:『手にとるようにわかる ブランディング入門』(金子大貴、 一色俊慶 著)
ブランディングにおけるロゴの役割

ブランディングにおけるロゴの役割を具体的に見てみましょう。
● 認知度の向上
● 他社ブランドとの差別化
● 自社や製品に対するイメージの形成
● 一貫したメッセージの発信
● 社内の帰属意識の向上
認知度の向上
企業やサービスのイメージを可視化させたロゴは、認知度の向上に役立ちます。繰り返し目にすることで顧客の記憶に残るからです。広告やWebサイト、商品パッケージなどさまざまな接点で効果を発揮します。
例えば、街中で何度も見かけることで、「どこかで見たことがある」という安心感が生まれます。初めて使う商品も手に取りやすくなるでしょう。こうした視覚的な接触の積み重ねが、ブランドの認知を高めていきます。
他社ブランドとの差別化
ロゴを制作することで、他社ブランドとの差別化も図れます。競合が多い市場において、顧客が「商品やサービスの違いがわからない」といったケースも珍しくありません。そのようななか、記憶に残るロゴはブランドを際立たせる役割を果たします。
強力なロゴであるほど顧客にブランドイメージを想起させ、製品やサービスの記憶を定着させるのに有効です。
自社や製品に対するイメージの形成
自社や製品に対するイメージの形成にも、ロゴの制作が欠かせません。
ロゴは、ブランドの視覚的要素であるビジュアルアイデンティティ(VI)の一部です。
ビジュアルアイデンティティは、企業やブランドが掲げるコンセプトや価値を、目に見える形で表したデザイン要素です。ロゴだけではなく、カラーやフォント、シンボルマーク、パッケージデザインなど、ブランドのイメージを統一的に伝えるための要素全般を指します。
ロゴの制作においては、ブランドカラーやキーグラフィックとともに、ブランドを統一するためのルールも形成します。ブランドに合ったロゴ、カラー、フォントを使えば、顧客に強い印象を与え、一貫したメッセージを伝えられるでしょう。
例えば、Amazonのロゴは「AからZまですべて揃う」ことと「顧客の笑顔」を表す矢印で、豊富な品揃えと顧客第一主義を象徴しています。
参考:『手にとるようにわかる ブランディング入門』(金子大貴、 一色俊慶 著)
一貫したメッセージの発信
ロゴは、デザインマネジメントの重要な要素の一つでもあります。ロゴを制作するなかで、企業のあらゆる制作物のトーン&マナーを統一するためのルールが設けられます。
単にロゴが新たに作られるだけでなく、ロゴ制作の過程を通して、一貫したメッセージを発信できるようになるでしょう。
社内の帰属意識の向上
ロゴは社外への訴求だけでなく、社内メンバーの意識にも影響を及ぼします。例えば、ユニフォームや社内報などに企業ロゴを展開すると効果的です。
統一されたロゴが共有されることで、ブランドに対する誇りや組織の一体感が生まれ、帰属意識の向上につながります。企業文化への理解も深まるでしょう。
ブランディングにおけるロゴに必要な3つの条件

効果的なロゴを作るためには、見た目の美しさ以上に、企業の価値観や立場を明確に伝えられるかどうかが問われます。ここでは、ブランディングにおけるロゴに必要な3つの条件を紹介します。
- 自社のブランドコアを可視化している
- シンプルで分かりやすい
- オリジナリティがある
- 関与者の想いの集積となっている
1. 自社のブランドコアを可視化している

ロゴは、企業やサービスのブランドコアを可視化したものであるべきです。ブランドコアとは、企業の以下の要素が重なる部分のことです。
● 自社のありたい姿
● 顧客のありたい姿
● 従業員のありたい姿
ロゴはただ目立てばいいというものではなく、形状や色、配置などがブランドの内面と一致している必要があります。言葉にしづらい企業の内面を、視覚的に伝えられるかが重要です。
自社のありたい姿は目指すべき姿や理由、顧客のありたい姿は顧客が企業や商品に望むことを意味します。そして、従業員が企業に望むこと、競合他社ができないことを踏まえて、ブランドコンセプトを定義しブランドコアを可視化させます。
2. シンプルで分かりやすい
ロゴはシンプルで分かりやすいことが条件です。芸術作品としての美しさではなく、商品や広告に掲載したときに認知しやすいかを重視して作成しましょう。
細かすぎるロゴや複雑なビジュアルは覚えにくいだけでなく、縮小表示されたときに視認性が落ちてしまいます。
視認性と記憶のしやすさが確保されていることは、ロゴの基本です。顧客が瞬時に認識することができて、覚えやすい構成が望ましいでしょう。
3. オリジナリティがある
ロゴはブランドのイメージを決めるものであり、オリジナリティが求められます。他社と似ているロゴでは記憶にも残りにくく、著作権や商標権侵害など法的なリスクが生じることもあります。
必ず市場調査を行い、競合と明確に差がつくデザインを意識しましょう。自社らしさが一目で伝わるようなロゴは、それだけでブランド価値を高めてくれます。他社にはない、独自の切り口やデザインで表現したロゴが理想です。
4. 関与者の想いの集積となっている
担当部署だけでなく、社員全員で意見を出し合い、感覚の地図を共有することが重要です。会社や製品のことを考え、それは何かを「ひと言で表す、考える、皆ですり合わせる」という過程は、社員が所有感を持てるようになる機会になります。愛されるブランドは、こうした共同作業の結果として生まれるものです。
ブランディングにおけるロゴ制作の流れ

ロゴ制作の流れは単なるデザイン工程ではなく、ブランドの本質を形にするためのプロセスです。大切なのは「どのように作るか」であり、ロゴそのものはプロセスの結果にすぎません。
ブランドコアを明確にし、社員と共有する
まず、自社のミッションやビジョン、提供価値を見つめ直し、「自分たちは何者なのか」「社会にどう貢献したいのか」といったブランドコアを明確にしましょう。ここで生まれる言葉やイメージが、後のクリエイティブの基盤となります。ブランドコアを可視化する際には、自社が大切にしているデザインのトンマナを加味しつつ表現することが重要です。
ロゴのテーマやコンセプトを決める際には、デザイナーや経営層だけでなく、社員や関係者を巻き込み、感覚の地図を共有することが大切です。
「会社や製品を一言で表すなら何か?」という問いを皆で考え、意見をすり合わせていくプロセスは、社員が自社ブランドに所有感を持つための貴重な機会になります。こうした取り組みによって、ロゴは全員の思いが込められた象徴となり、社内外から長く愛される存在へと育っていきます。
クリエイティブの積み重ねでロゴデザインを形にしていく
そのうえで、デザイナーは調査や共有で得られた顧客や社員の言葉・イメージをもとに、象徴的な形や色、言葉を新たに創造していきます。これは「ロゴを決める」作業ではなく、皆の思いを可視化するための試行錯誤の連続です。実際には何十、何百もの案を生み出し、緻密にブラッシュアップを繰り返すことで、ようやく一つの形に辿り着きます。
色やフォントも重要ですが、「青=信頼感」「赤=情熱」といった一般的な印象を当てはめるだけでは不十分です。
ブランドの世界観やアイデンティティに合わせ、コーポレートカラーやサブカラーの組み合わせ、フォントの硬さ・柔らかさ、視認性なども含めて総合的に検討しなければなりません。こうしたデザイン要素の統合は、専門的なクリエイティブ領域であり、実績や信頼のあるプロに任せることをおすすめします。
さらに、関係者と検証を重ね、修正を加えることで精度を高めていきます。ここで重要なのは好みではなく、ブランドの象徴としてふさわしいかどうかという視点です。
商標登録でロゴを守り、ブランド資産として活用する
ロゴを自社の知的財産として保護するために、完成後は必ず商標登録を行いましょう。未登録のまま使用すると、第三者に登録されたり模倣されたりといったトラブルのリスクが生じてしまいます。商標登録を行うことで、法的な正統性を持って企業の資産として守ることができます。
日本国内では出願から登録まで通常7〜9ヶ月の期間がかかり、費用は自分で出願する場合は約3万円から、特許事務所に依頼する場合は14万円以上が一般的です。商標権は10年間有効で、更新することで半永久的に権利を維持することが可能です。
審査の結果によっては登録が難しいケースもあり、将来的に海外展開を視野に入れる場合は国際商標制度を利用する必要もあります。早めの対応によって、ブランドの象徴を確実に保護できるのです。
このように、ロゴは「色を決める」「フォントを決める」といった単純なステップの積み上げで生まれるものではありません。思いを定義し、共有し、創造し、磨き上げ、守っていくプロセスの中で育まれ、その過程が濃ければ濃いほど、ロゴはブランドの象徴として長く愛され続けるのです。
愛されるブランド・ロゴを生むポイント

愛されるロゴを生むポイントは前述の通り下記です。
● 自社のブランドコアを可視化している
● シンプルで分かりやすい
● オリジナリティがある
● 関与者の想いの集積となっている
ロゴは制作後、長期的に使われ続ける存在です。しかし、長期で使用する場合、時間の経過とともに古く見えてしまう可能性があります。企業ロゴや製品ロゴを制作する場合は、今の流行りだけでなく、長期的に使用できるデザインで制作するのがよいでしょう。
時代に左右されないベーシックな形状や色使いなら、長く使い続けても違和感がありません。持続可能なデザインを意識しましょう。
ブランディングにおけるロゴ制作の成功事例
最後に、ブランディングにおけるロゴ制作の成功事例を紹介します。これからロゴ制作に取り組もうとしている方は、ぜひ参考にしてみてください。
● 企業ブランディング「KLASS株式会社」
● サービスブランディング「OREX®」
● 地域ブランディング「八王子芸術祭」
企業ブランディング「KLASS株式会社」

畳製造・壁紙施工の省力化機器、厨房機器・各種メカトロ機器を製造販売する総合FAメーカー、KLASS株式会社。同社では、2021年から2023年にかけて、CI(コーポレート・アイデンティティ)再構築プロジェクトを実施しています。
プロジェクトでは新たなCIを踏まえ、社名とともにロゴを刷新しました。各種ツールへ展開しました。また、マニュアルを用意し、ブランドの統制も強化しています。
社員エンゲージメント調査では、「社名変更によって会社の目指すべき道が明らかになった」との回答が大半を占める結果になりました。また、社外からも新社名とロゴに対する好意的な反応が多数挙がりました。大胆なリブランディングにより、業界をリードする同社のプレゼンスをさらに高められた事例です。
サービスブランディング「OREX®」

株式会社NTTドコモが手がける「OREX®」。多様なグローバルベンダと連携して世界各国でOpen RANを提供するサービスブランドです。
立ち上げ当初は新事業としてのサービス内容が伝わりにくく、潜在顧客への効率的なブランド浸透ができていない状況でした。そこで同社では、ブランド構築に関するコンペティションによるパートナー会社選定からプロジェクトをスタートしました。
当プロジェクトのメインスコープは、新事業のビジョン、ブランドロゴ、メッセージを策定しています。そのため、自分たちの考えや想いに対する理解と、新しい視点を併せ持ったパートナー会社を選ぶことが重要だと考えました。
ロゴ制作では、多様性やOREX®というサービスの本質でもある柔軟性を採り入れたデザインを意識。社内メンバーの共通認識を醸成できました。また、国内・海外でのメディア露出の増加に伴い、サービス認知も向上しています。
地域ブランディング「八王子芸術祭」

八王子では、長年音楽祭を実施していました。しかし、八王子市民を対象とした世論調査では、芸術活動を行っている人口が増えることはなく、横ばいで推移していました。
こういったなかで、音楽以外の芸術にも親しめる芸術祭を実施したい、という想いを抱いていたのです。ところが「知見がなく、先立ってコンテンツのみ決定している」状況でした。
そこでブランディングプロジェクトでは、芸術祭のコンセプトを策定しました。メインビジュアルやロゴも制作しています。パンフレットやLPにも展開を行い、一貫した訴求ができる状態になりました。
ロゴデザインはさまざまな形をシミュレーションしたうえで、巡回型の芸術祭であることを伝えやすい「円形」のものに決定しました。
その結果、来場者数が目標数値を達成するに至ったのです。参加したアーティストや来場者からも好評の声が多数挙がっています。次回以降の芸術祭にて作品を出展したいという問い合わせがあるなど、八王子芸術祭の認知度UPや魅力の訴求を実現できました。
ブランディングのロゴ制作なら大伸社コミュニケーションデザイン
本記事では、ブランディングのロゴ制作について詳しくご紹介しました。ロゴ制作は、ただアイコンを作ればよいというものではありません。企業や製品のアイデンティティを明確にしたうえで、顧客にイメージを届けられる設計が重要です。
とはいえ、自社にノウハウのない状態で効果的なロゴを制作することは難しいものです。ロゴ制作を実施する際は、プロのアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。
ぜひ、株式会社大伸社コミュニケーションデザインにご相談ください。ロゴ制作をはじめとする豊富なブランディング実績と、ブランディングに関するプロが、自社だけでは難しいブランドアイデンティティの定義や成果のでるロゴの制作をサポートさせて頂きます。