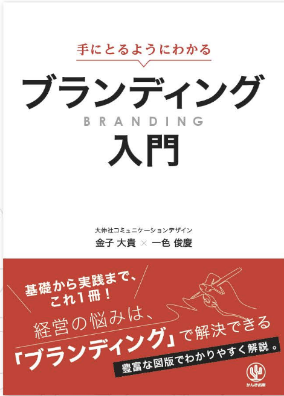働き方やキャリアの在り方が多様化する今、自分の持ち味や強みをどう表現し、どのように伝えていくかが問われる時代となりました。そこで注目されているのが、自分自身の魅力や考え方を整理して的確に伝える「セルフブランディング」です。
本記事では、セルフブランディングについて、取り組むメリットや実践ステップ、注意点などをまとめました。後半では、成功事例やよくある質問についても紹介します。セルフブランディングについてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
- 目次
自分をブランディングする「セルフブランディング」とは?
セルフブランディングとは、その名の通り、自分自身をブランディングすることです。自らを一つの「ブランド」としてとらえ、その価値を高めていく考え方を指します。
ブランドは「見聞きした瞬間、頭に浮かぶ独自のイメージ」のことです。そして、ブランディング、すなわちブランドを形成することは、「頭に浮かぶ独自のイメージを確立するための努力」だといえます。
詳しくは「ブランディングとは?意味や目的・課題別の取り組み方も紹介 」をご覧ください。
企業は、ターゲット顧客から企業のあるべきブランドイメージを連想してもらうことを目指す必要性があります。ブランド力を高めることで、ステークホルダーから選ばれます。
同様に、個人も信頼性や実績、情報発信を通じて、「この人に仕事をお願いしたい」と思われる存在になることが可能です。
特に近年はインターネットやSNSの普及により、セルフブランディングに取り組みやすい環境が整ってきています。
自分をブランディングをすることが注目される背景
企業ではなく自分という個をブランディングすることが注目される背景には、1997年のトム・ピーターズが提唱した「The Brand Called You」の普及があります。これは「自分自身がブランドである」(パーソナル・ブランディング)という考え方です。
従来の終身雇用モデルの崩壊や新自由主義的な価値観の浸透とともに、この考えは個人が市場で自らを差別化し、価値を発揮する手段として広がりました。
近年では副業の解禁や多様な働き方の推進によって、個人が自立をしたり、キャリア形成をしたりする手段としてセルフブランディングがより注目されています。
参考:セルフ・ブランディングと パーソナル・ブランディングの関係性 カラータイプ理論からの考察│関西学院大学経営戦略研究科(佐藤 善信/河野 万里子/相島 淑美)
セルフブランディングのメリット

セルフブランディングのメリットは以下の通りです。
- 競合と差別化できる
- 集客のための広告費を削減できる
- ビジネスチャンスが増える
- ファンやリピーターを獲得できる
- 価格競争から脱しやすくなる
- 長期的な資産になる
1. 競合と差別化できる
セルフブランディングの大きなメリットは、競合と差別化できることです。
自分と同じようなサービスを提供している人や、立場の人が多い場合、自分の価値観や姿勢を的確に発信してブランド化できると差別化につながります。価格や機能など表面的な比較ではなく、「誰に依頼するか」で選ばれる状況を作り出すことができます。
2. 集客のための広告費を削減できる
セルフブランディングが成功すれば、多額の広告費をかけずとも集客が安定するようになります。これはフリーランスや個人事業主で仕事を請け負っている人、また企業内でも個人の名前で集客をしている人にとって有効です。
発信を通じて関心を持ってくれる人が増えれば、集客や営業にかけるコストを抑えられるでしょう。「この人なら信頼できそう」「話を聞いてみたい」と思ってもらえれば、無理に自分を売り込む必要もなくなります。
3. ビジネスチャンスが増える
セルフブランディングに取り組むことで、自分の考え方や価値観に共感する人が自然と集まりやすくなります。ビジネスチャンスが増えて、新規契約や販路拡大の話が持ち上がることもあるかもしれません。
また、共同の企画を持ちかける際や、就職・転職希望先にアプローチする際にも、好意的な反応をしてもらいやすくなるでしょう。
4. ファンやリピーターを獲得できる
セルフブランディングにより競合と差別化することで、ファンやリピーターも獲得しやすくなります。共感をベースに築かれた信頼関係は時間が経っても途切れにくく、知人への紹介やSNSでのシェアなどで広がっていく可能性もあります。
ファンやリピーターが増えれば、売上も安定しやすくなるでしょう。
5. 価格競争から脱しやすくなる
価格競争から脱しやすくなることも大きなメリットです。
独自性のあるポジショニングを確立できれば、同じサービスでも「この人にお願いしたい」と思ってもらえます。自分のブランド力が高まるほど価値を感じてもらえるようになり、価格競争から外れることができます。
6. 長期的な資産になる
セルフブランディングを通して築いた信頼や実績は、勤め先や立場が変わっても残ります。また、SNSやブログ、ポートフォリオなどの情報は、将来にわたって自分の価値を支えてくれる長期的な資産となるでしょう。
業務内容や肩書きが変わる場面でも、セルフブランディングができていると自分自身の価値を明確にし、強みや独自性を発揮しやすくなります。そのため、人脈やキャリアの幅を広げ、将来的な成功につなげることが可能です。
自分をブランド化する「セルフブランディング」の進め方

以下では、セルフブランディングの進め方をまとめました。これからセルフブランディングに取り組もうとしている方は参考にしてみてください。
自己分析で自分の軸を見つける
まずは、自分自身を理解することから始めましょう。自分が何を大切にしているか、どのようなことに喜びややりがいを感じるかなどを掘り下げて「自分の軸」について考えます。
たとえば、「誰かの役に立つ瞬間にやりがいを感じる」「成果が数字として見えることに達成感を持てる」など、日常の中にヒントがあるかもしれません。また、周囲からどう見られているか、どのような言葉をかけられることが多いかなども客観的な材料となります。
| 具体例 ・大切にしている価値観:「お客様に安心感を与えること」「長期的な信頼関係を構築すること」 ・喜びを感じる瞬間:相談されて、相手が前向きになる瞬間 ・他者から言われること:「聞き上手」「いつも丁寧で落ち着いている」 ・上記から得た自己理解:人に安心感を与えるコミュニケーションを軸としたブランディング戦略 |
ターゲットを絞る
自分の軸が定まったら、自分が届けたい相手を具体的にイメージしてターゲットを絞りましょう。「誰に向けて何を発信するのか」が曖昧なままでは、自分の魅力が伝わりにくくなってしまいます。
たとえばコンサルティングサービスを展開する場合、起業初期の人に向けるのとベテランの人に向けるのとでは、伝え方も切り口も異なります。誰に届けたいのかを明確にすることで、伝える言葉に芯が通り、相手の心に届く発信ができるようになります。
| 具体例 ・ターゲット:「育児と仕事の両立に悩む30代の子育てママ」をターゲットに設定 ・届けたい内容:時間管理術や心の余裕の作り方 ・伝え方:堅苦しくない共感ベースの言葉遣いで「私もそうだった」と語りかけるスタイル ・避けること:ビジネス用語ばかりで威圧的に感じさせる発信 |
見せたい“イメージ”を決める
誰に発信するのかと併せて、自分がどう見られたいかも整理しておきましょう。例を挙げるなら、「親しみやすさを感じてほしい」「誠実さや信頼感を重視したい」「専門的で頼れる印象を与えたい」などです。
見せたい“イメージ”を決めることで、発言のトーンや選ぶ写真、プロフィール文の構成などを一貫して整えられます。無理に自分を作り込む必要はありませんが、意図を持って印象を設計しておくと発信にぶれがなくなります。
| 「いつでも頼れて、信用ができる大人の女性」を目指すと決めた場合の具体例 ・発言トーン:優しく丁寧でありながら芯がある ・写真:笑顔の自然体ポートレート、明るい屋外で撮影 ・デザイン:温かみのあるナチュラル系(淡いベージュやグリーンを使用) |
プロフィールを作成する
次に、プロフィールを作成しましょう。SNSやブログ、Webサイトなど、プロフィールを見て興味を持つ人は多くいます。そのため、名前や肩書きだけで終わらせず、自分の想いや背景を伝える構成にすることがポイントです。
何を大切にしているのか、どのような経験を積んできたのかなどを、自分の言葉で表現しましょう。ただの経歴紹介ではなく、ストーリー性を意識して伝えることで共感を得やすくなります。
| プロフィールの例 3児の母であり、フリーランスのライフスタイルコーチ。 育児と仕事に追われて自分を見失いかけた30代を経て、現在は「私らしく働く」生き方をコーチング・サポートしています。 元はIT企業でマーケティング職として10年間勤務。その経験を活かし、今は個人事業主の方向けにブランディング支援も行っています。モットーは「無理なく、自然体で」。 好きな時間は、朝のコーヒーと子どもたちと過ごすおやつタイム。 |
情報発信をする
準備が整ったら、自分の考えや経験を外に向けて発信します。SNS、ブログ、note、YouTubeなど、使える媒体はさまざまです。
まず、続けられる方法で始めることが肝要です。最初から完璧を目指す必要はありません。むしろ、自分の言葉で自然体のまま伝えていくことが信頼につながるケースもあります。日々の気づきや、過去の経験、試行錯誤の記録なども立派なコンテンツになります。
SNS発信の例
- 内容例:「朝活で30分自分の時間をつくるコツ」「ママ起業初期にやってよかった5つの習慣」「うまくいかない日こそ、自分を見つめ直すチャンスだった」
- 頻度:週に2回の投稿、1回はストーリーズでQ&A
- 投稿方法:Canvaで投稿画像を作成、Laterで予約投稿
反応を見て改善する
発信して終わりではなく、その後の反応を見ながら調整していくことも忘れないようにしましょう。どの投稿に反応が多いのか、想定した伝わり方になっているかなどを振り返ることで、改善を重ねていきます。
同時に、軸がぶれていないか、無理をしていないかなど、「自分らしく在れているか」も定期的に確認しましょう。自分なりのスタイルを整えていくことがポイントです。
| 改善例 ・Plan(計画):「ビジネス寄りの専門的な情報」を中心に展開し、信頼性や実績を伝えることを重視。 ・Do(実行):実際にビジネスノウハウやマーケティングの知識などを中心に投稿を開始。 ・Check(検証):思ったほどの反応は得られず、いいね数や保存数、コメントも伸び悩む。試しに方向性を変えて「育児の葛藤を赤裸々に語った投稿」をアップしたところ、コメントや保存数が急増。 ・Act(改善・対策):発信内容を「共感・リアル寄り」にシフトして、キャッチコピーも柔らかく変更。 |
セルフブランディングの注意点

セルフブランディングに取り組む際は、以下のポイントに注意しましょう。
- 一貫性を保つ
- 過度な演出を避ける
- 自分本位にならないように注意する
- 目的を明確にする
- 見た目・ビジュアルにもこだわる
一貫性を保つ
コンセプトに対して発言や発信内容などの一貫性がないと、「何を大事にしている人なのか」が伝わりにくくなります。共感してもらうためには、考え方や表現に芯があることが重要です。
たとえば、普段は穏やかな文面を綴っているのに、急に攻撃的な投稿をすると、違和感を与えてしまいます。一度決めた方向性や軸を大きく変えることは避け、必要があれば言葉のトーンやテーマを少しずつ調整する程度にとどめると自然でしょう。
過度な演出を避ける
過度な演出は避けましょう。実績や経験を無理に大きく見せようとすると、かえって信頼を失います。見栄えの良さを優先して誇張した表現をしてしまえば、「本当なの?」「話が大きすぎる」と疑念を持たれる原因となります。
印象づけたい場面であっても、誠実さを意識して伝えることが大切です。
自分本位にならないように注意する
自分の考えや強みを発信することは重要ですが、押しつけのようになっていないか注意しましょう。相手の立場を意識して、「どのような人にどう役立つか」という視点で伝えることがポイントです。
たとえば、自己紹介や実績紹介でも、「このような経験があったので、同じような悩みを持つ人の力になりたいです」といった書き方をしてみましょう。関係性を築くことで相手にメリットがあることが伝わりやすくなります。
目的を明確にする
セルフブランディングに取り組む場合、必ず目的を明確にしましょう。ただ何となく始めると続かなくなることが多く、方向性に迷ったり、発信に意味を見出せなくなったりしてしまいます。
たとえば「キャリアアップしたい」「ビジネスチャンスにつなげたい」など、目的を具体的にしておくことで、迷ったときの判断基準になります。
見た目・ビジュアルにもこだわる
どれほど中身が良くても、第一印象が思わしくなければ受け取られ方が変わってしまいます。SNSのアイコンやカバー画像、プロフィール写真など、ビジュアル要素もセルフブランディングの一環です。特に、以下のようなポイントに気をつけましょう。
| NG例 ・SNSアイコンが適当 ・写真が古い ・デザインに統一感がない |
色やデザインに統一感があると、印象に残りやすくなります。適当な写真やデザインを避け、イメージに合った清潔感のあるものを選ぶようにしてみてください。
セルフブランディングの成功事例

ここからは、セルフブランディングの成功事例をご紹介します。これからセルフブランディングに取り組む方は参考にしてください。
- フェリシア ラボ代表 高橋和子氏
- ジャパネットたかた創設者 髙田明氏
- ソフトバンクグループ代表 孫正義氏
フェリシア ラボ代表 高橋和子氏
家事と育児に追われていた専業主婦から、生活改善のプロとして事業を始めた高橋和子氏。3Sコーディネーター1級など収納術に関する資格を取得し、整理収納コンサルタントとして活動をスタートさせた創業当初は同じような講師や専門家が多く、差別化に苦労していたといいます。
転機となったのは、自分がこれまで経験してきた親の介護経験や転勤族の妻としての強みを活かし、コンテンツとして発信しはじめたことでした。実体験をベースにした情報はリアリティがあるため多くの共感を呼び、SNSやブログで注目されるようになります。
その後は、テレビや雑誌への出演、講演依頼も増えたといいます。個人のスキルを軸にしたセルフブランディングの好例となりました。
ジャパネットたかた創設者 髙田明氏
ジャパネットたかた創設者の髙田明氏は、自らテレビに出演して商品の魅力を伝えるスタイルで注目を集めた人物です。独特な話し方は視聴者の記憶に残り、モノマネの対象になるほどのインパクトを放ちました。
商品に対して使う人の生活をイメージしながら語りかけるように紹介する姿勢により、「信頼できる人が勧めている」という印象を確立しています。テレビショッピングの視聴率は上昇し、ジャパネットたかたのブランド力は大きく向上しました。
ソフトバンクグループ代表 孫正義氏
ソフトバンクの創業者・孫正義氏は、技術革新を通じて社会に貢献するという明確なビジョンを掲げてきました。
TwitterをはじめとするSNSで積極的に発言し、業界関係者だけでなく一般の人々とも広くコミュニケーションをとる姿勢が話題となりました。技術や経済に関する内容だけでなく、社会課題や未来への展望など多岐にわたる内容が共感を呼び、フォロワー数が拡大したのです。
ネットワークの広がりとブレない理念の発信が、孫氏のブランド価値を支えています。発信の影響力を戦略的に活かした好例といえるでしょう。
セルフブランディングを学べるおすすめの本

以下では、セルフブランディングを学べるおすすめの本をまとめました。
- パーソナルブランディング 最強のビジネスツール「自分ブランド」を作り出す
- 「売れる個人」のつくり方
詳しく解説します。
パーソナルブランディング 最強のビジネスツール「自分ブランド」を作り出す
本書は、「個人の能力にレバレッジをかけるための最強ツール」としてセルフブランディグについて触れた一冊です。
著者は米国No.1カリスマ・パーソナルブランド・コンサルトであるピーター・モントヤ氏。会社や組織に依存しないキャリアを目指す方には特におすすめです。
| 書名 | パーソナルブランディング 最強のビジネスツール「自分ブランド」を作り出す |
| 出版社 | 東洋経済新報社 |
| 著者 | ピーター・モントヤ |
| 出版年 | 2005年(日本語版) |
「売れる個人」のつくり方
本書は、“売れない個人”から“売れる個人”へと変わるための実践書。フリーランスや個人事業主、転職希望者など、自分の名前でキャリアアップを目指したい人におすすめの一冊です。
「何を発信すればよいかわからない」「自分の強みが見つからない」。こうした悩みに対して、著者が実践してきたプロセスをもとに、ステップバイステップでセルフブランディングの方法が解説されています。心構えから戦略、発信まで、包括的に学べる内容です。
| 書名 | 「売れる個人」のつくり方 |
| 出版社 | clover出版 |
| 著者 | 安藤美冬 |
| 出版年 | 2021年 |
セルフブランディングでよくある質問
最後に、セルフブランディングに関する疑問や誤解されやすいポイントについて、質問形式でまとめました。取り組みを進める際の参考にしてみてください。
女性のセルフブランディングのコツや気を付けることは?
女性の場合、メイクや服装、髪型、パーソナルカラーなどを意識するだけで印象が大きく変わります。ただし、無理に着飾る必要はありません。自然体で発信すること、背伸びをしすぎないことが、セルフブランディングに取り組む際の重要なポイントです。
セルフブランディングが痛い・うざいと言われるのはなぜ?
発信内容が現実離れしていたり、過度な自慢話ばかりになっていたりしないか注意が必要です。周囲から違和感を持たれて、「痛い」と言われてしまうことがあるかもしれません。
セルフブランディングとパーソナルブランディングは何が違いますか?
セルフブランディングとパーソナルブランディングはほぼ同じ意味で使われることが多く、厳密な違いはありません。あえて使い分ける場合も、その境界はさまざまです。
たとえば、「セルフブランディング」がビジネス寄りの文脈で使われ、「パーソナルブランディング」はライフスタイルやプライベートを含む広い意味で使われることがあります。組織に属しない個人事業主などが「セルフブランディング」を行い、組織内の一個人が組織のブランディングの方向性に沿って「パーソナルブランディング」を行うとするケースもあります。
セルフブランディングとセルフプロモーションは何が違うの?
セルフブランディングは、「ブランド力を高める」ために活動を続けていく長期的な取り組みです。一方のセルフプロモーションは、「販売促進・集客のためのPR活動」に近いものです。いずれも重要ですが、目的や文脈によって使い分けるとよいでしょう。
セルフブランディングを活かしてビジネスを拡大
本記事では、セルフブランディングの基本から進め方や注意点、成功事例まで幅広くご紹介しました。
自分の価値や考え方を整理し、他者にわかりやすく伝えていくことで、売上やビジネスチャンスの拡大が期待できます。
とはいえ、ブランディングを全て一人で考え、形にしていくことは簡単ではありません。発信内容に一貫性を持たせたり、適切な表現方法を選んだりするには、専門的な思考や客観的な視点が必要な場面もあります。
弊社は、ブランド策定・インナーブランディング・アウターブランディングの3つの領域から企業・プロダクトのブランディング支援を行っている企業です。
ブランディング戦略に行き詰まっている、具体的な問題を抱えているなどでお困りの場合は、ぜひ弊社までご相談ください。