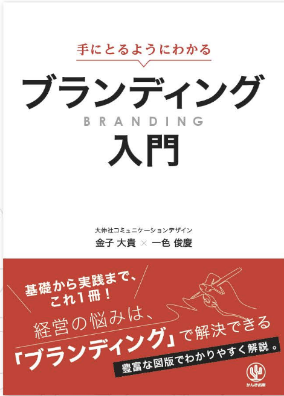インナーブランディングとは?
インナーブランディングとは、企業の理念やビジョン、価値観を社内の従業員に共有し、理解・共感を促す取り組みです。ブランド体現が進むと、その結果エンゲージメントやモチベーションが向上し、ひいては生産性のアップや離職率の低下をもたらします。こうした内部施策が整うことで、外部に向けたブランディングの基礎が築かれ、顧客に対してブレのない一貫したブランド体験を提供できるようになります。さらに、社内からブランドを育んでいく取り組みを通じて企業文化が強固になり、その積み重ねが長期的な企業価値の向上へとつながります。
インナーブランディングの定義とは?
インナーブランディングとは、「『ブランド定義』で定めた『会社の目指すべき方向性』や『顧客に抱いてほしいイメージ』『ブランドコア / P-MVV(パーパス・ミッション・ビジョン・バリュー)』を社員に浸透させる社内コミュニケーションの取り組み」です。
企業ブランディングを始めるにあたっては、まずはインナーブランディングによってある程度社内に浸透させた後に、アウターブランディングに着手するという段取りが理想的なシナリオです。その理由は、社内に浸透しないうちに社外に対してブランディング活動を行っても、一貫性がなくなってしまい、顧客等に混乱を与えてしまう可能性が高まるからです。
インナーブランディングの目的・効果とは?
インナーブランディングが目指すのは、企業理念やビジョン、価値観を社員一人ひとりに定着させ、行動を“自分ごと”として捉えさせることです。取り組みが浸透すると、社員のエンゲージメントが高まり、離職率低減や定着率向上が実現し、組織全体のパフォーマンスが強化されます。また、評価や意思決定の基準が統一されることで、業務プロセスが効率化され、生産性の向上にも寄与します。結果的に、社内外において一貫したブランド体験を提供するための堅牢な基盤が築かれ、長期的には企業価値の持続的な向上が期待できるのです。
- 目次
インナーブランディングと混同されやすい言葉との違い
社内の従業員にブランド理念や価値観を浸透させる内部戦略を指す用語として「インナーブランディング」がありますが、類似した呼び方が多いため混乱しやすいのが実情です。まずは「インナーブランディング」とほぼ同義に用いられる「インターナルブランディング」の名称の違いを整理し、続いて顧客や市場に向けた外部戦略である「エクスターナル/アウターブランディング」との相違点を紹介します。これらの用語を正確に使い分けることで、社内外で統一感のあるブランド運営を実現しましょう。
インナーブランディング vs インターナルブランディング:社内ブランド戦略の呼び名の違い
インナーブランディングとインターナルブランディングは、企業内部でブランド価値を浸透させる役割を担う点で同じアプローチを指します。どちらの呼称を用いても、従業員が企業のミッションやビジョンを深く理解し、日々の業務でその価値観を体現できるようにする仕組みを意味します。実際には、用語の違いが組織文化やコンサルタントの手法に影響を与える場合もありますが、目的とプロセスは本質的に一致しています。
両者は呼称の違いだけであり、実施する施策や目的に本質的な差はありません。どちらも社内向けに企業理念や行動指針を共有し、従業員の理解・共感を深める活動を指します。呼び分けは企業文化や外部コンサルタントの用語体系に依存しがちです。
インナーブランディング vs エクスターナル/アウターブランディング:内外向け戦略の棲み分け
企業内コミュニケーション施策の一環として実施されるインナーブランディングは、従業員一人ひとりへのブランド浸透を目的とした内部戦略です。一方で、顧客や市場を対象とするアウターブランディング(エクスターナルブランディング)は、外部に向けてブランドイメージを発信する活動を指します。前者がしっかりと基盤を築くことで、後者のメッセージは一貫性と信頼性を獲得しやすくなります。さらに、内部戦略と外部戦略を連携させることで、ブランド全体の強化と持続的な価値向上が実現します。
インナーブランディングが重要な理由とは?
社内向けのブランディング活動に時間を割いて取り組もうという会社はまだまだ少ないようですが、インナーブランディングこそがブランディングの肝であり、特に中小企業にとっては、最も重要な活動だと言っても過言ではありません。一体なぜなのでしょうか?
ユーザーの頭の中でブランドを作るのは、ブランドとユーザーの接点である「ブランド・タッチポイント」での経験です。そのブランド・タッチポイントにおいて、ブランドを伝えるのは結局は人なのです。口コミのようにユーザーが伝えてくれる場面もありますが、大半のタッチポイントにおいては、ブランドを伝えるのは、そのブランドの経営者および営業などをになっている社員です。意外と思われるかもしれませんが、有事があった際に対応する管理職という人材も、ここに含まれるのです。極端な例ですが、社長が「お客様第一の経営をします」と言っているのに、営業が顧客にとって必要のないものを売りつけようとしていたらどうでしょうか。「何が顧客第一だ」と会社に対する満足度は低下し、離れていく顧客も出てくるはずです。
インナーブランディングが社員にしっかり定着していれば、店舗オペレーションから IT システムまで、何もかもが変わってきます。逆に社員に「会社の目指すべき方向性」や「顧客に抱いてほしいイメージ」「ブランドコア / P-MVV(パーパス・ミッション・ビジョン・バリュー)」という価値観が浸透しない限り、顧客に対して一貫性のある「ブランドメッセージ」が伝わることはありません。半分の社員が理解していたとしても、残り半分の理解していない社員が台無しにしてしまうことでしょう。
インナーブランディングのメリットとは?
インナーブランディングを行う前におさえておきたい、10個のメリットについて説明します。
メリット1. インナーブランディングで従業員エンゲージメント向上&離職率低下
従業員にブランド価値を丁寧に届ける取り組みを行うことで、自社への誇りが自然と高まり、エンゲージメントが強化されます。その結果、離職率の低下だけでなく、部署を越えた連携強化や主体的な業務提案が増え、組織運営はより安定化します。また、ブランドに共感した社員が対外的にもブランドアンバサダーとして機能し、顧客満足度や採用評価の向上にも好影響を及ぼします。さらに、社員同士が共通の目標意識を持つことでチームワークが強化され、日々のコミュニケーションも活性化します。目に見える成果だけでなく、プロセス自体に価値を見出せるようになるため、長期的に社員満足度が底上げされ、定着率向上にも寄与します。
メリット2. インナーブランディングで社員のブランド理解が深まる
ブランド理念やビジョンをわかりやすい言葉や事例に落とし込む施策によって、社員一人ひとりのブランド理解が格段に深まります。例えば、ワークショップやケーススタディ、ロールプレイを通じて「なぜこの価値観が重要なのか」を体感すると、日常の業務判断にも自然とブランド精神が反映されるようになります。こうした体験型の学習機会を定期的に設けることで、社内の隅々まで共通認識が広がり、部署を越えた連携や顧客対応にも一貫性が生まれます。結果として、ブランドが生きた文化として根づき、組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。加えて、社内ワークショップや勉強会を通じて実践例を共有すると、抽象的だった価値観が“自分ごと”となり腹落ち度が高まります。理解が深まるほど、顧客対応や提案内容にも一貫性が生まれ、ブランドの信頼性向上につながります。
メリット3. インナーブランディングでモチベーションを高める
インナーブランディングを通じて、社員には企業のミッションへの共感と自分の役割を再認識するきっかけが生まれます。具体的には、ミッションをテーマにしたワークショップや事例共有を行うことで、「なぜ自分の仕事が企業の目標達成に不可欠なのか」が明確になります。その結果、社員一人ひとりのモチベーションが自然と高まり、指示を待つのではなく能動的に課題解決に取り組む姿勢が育まれます。さらに、成功体験を社内で共有する仕組みを設けることで、小さな成果が次の挑戦への原動力となり、組織全体の活力向上にもつながります。また、成功体験やフィードバックを社内で可視化することで達成感が広がり、さらに意欲をかき立てます。個々の努力がブランド貢献に直結していると感じられると、日々のチャレンジ精神も強まり、組織全体の活力が高まります。
メリット4. インナーブランディングで生産性を高める
企業がインナーブランディングを通じて目指すべき目標や価値観を明確にし、それを社内で共有すると、社員一人ひとりが同じ方向を向いて業務に取り組むようになります。共通のゴールがあることで、部署や立場を超えた意思決定のスピードが上がり、迷いや衝突が減少します。その結果、業務プロセスの無駄が削減され、チーム全体の動きがスムーズになっていきます。こうした取り組みは最終的に、生産性の向上という具体的な成果へとつながります。加えて、業務プロセスや評価基準がブランド価値に沿って整備されることで、無駄が削減されます。明確なガイドラインに基づいた行動が習慣化されると、属人的な対応も減り、チームとしてのパフォーマンスが安定的に向上します。
メリット5. インナーブランディングで組織文化を形成・強化できる
企業がインナーブランディングに取り組むことで、経営層や人事部門は共通の価値観や行動規範を明文化し、それを従業員に浸透させる仕組みを築きます。一方、従業員はその価値観を日常業務や行動に反映させることで、組織全体に統一感が生まれていきます。このようにして形成された共通意識は、社内のコミュニケーションを円滑にし、部署や職種を超えた一体感を育てていきます。結果として、持続的な成長を支える強い企業文化が醸成・強化されるのです。特に、日常的な社内コミュニケーションやイベントを通じて価値観を体験的に学ぶことで、言葉だけでない“文化”として根づきます。トップダウンだけでなくボトムアップの活動も並行すると、双方向の信頼関係が強まり、文化の定着率が高まります。
メリット6. インナーブランディングが競争優位性・企業価値を高める
インナーブランディングにより社員がブランドの差別化ポイントを理解・体現すると、市場競争での優位性が強化され、企業価値の向上につながります。ブランドの一貫性が社内外で評価されると、顧客や株主からの信頼度も増加します。さらに、社員が自らブランドのアンバサダーとして動くことで、口コミやリファラル採用など多面的な価値創出が促進され、持続的な成長基盤が築かれます。
メリット7. インナーブランディングがアウターブランディングの土台を築く
インナーブランディングで内部のブランド理解が進むと、外部向けのメッセージにも一貫性が生まれます。これがアウターブランディング成功の強固な基盤となります。内外でズレのないブランドストーリーは、広告やPRの説得力を高め、顧客接点ごとの体験価値を向上させます。また、社員自らがSNSや口コミでブランドを発信することで、オウンドメディアとしての効果も期待でき、外部施策との相乗効果が生まれます。
メリット8. インナーブランディングで一貫したブランドメッセージを発信
インナーブランディングは、社内で統一された言葉やビジョンを共有することで、対外的にもブレないブランドメッセージを発信できるようになります。統一された用語やストーリーを社員全員が使うことで、営業資料やカスタマーサポートの対応においても一貫性が担保されます。その結果、顧客との信頼関係が深まり、リピート率や紹介件数の向上にもつながります。
メリット9. インナーブランディングで企業の魅力を高める
インナーブランディングにより社員が自社に誇りを持つと、その魅力が顧客や求職者にも自然と伝播し、企業イメージが向上します。社内のリアルなストーリーや成功体験を外部に発信することで、採用ブランディングやPRコンテンツとしても活用可能になります。社員が語るブランド価値は信憑性が高く、外部ターゲットへの訴求力が強まります。
メリット10. インナーブランディングで採用活動を効率化
インナーブランディングで社内のブランド愛が高まると、従業員自身が自社を推薦しやすくなり、求職者への説得力も増します。これにより、採用活動の効率化が実現します。実際、社内アンバサダー制度を導入して社員が候補者を紹介する仕組みを整えると、採用コストの削減やミスマッチの防止にもつながります。自社のリアルな魅力を内部から発信することで、カルチャーフィットする人材獲得が加速します。
さらに、インナーブランディングを採用プロセスに活かすには、スキル・マインド・カルチャーフィットの3軸で評価基準を具体的に設計します。面接設問は「当社ミッションに共感したエピソード」「バリュー体現事例」を盛り込み、ブランド理解度を定量的に判断します。加えて、行動事例ベースの質問設計により、候補者の実践力を可視化できます。面接官には基準の統一とバイアス排除を目的としたトレーニングを実施し、公正な評価を担保します。こうした評価設計と運用によって、採用の質とスピードがさらに向上し、効率化が加速します。
インナーブランディングのデメリットとは?
インナーブランディングは多くのメリットがある一方で、企業が取り組む際にはいくつかの負担やリスクも伴います。特に押さえておきたい3つのデメリットをご紹介します。
デメリット1. インナーブランディングは時間とコストがかかる
インナーブランディングは、企業の現状分析からブランド理念の言語化、社内施策の設計・実行・定着まで、一連のステップを着実に進める必要があります。そのため、ワークショップや研修、コミュニケーションツール開発などに数カ月〜数年を要し、専任チームや外部コンサルタントのサポートが欠かせません。さらに、オンライン・オフライン両面のコンテンツ制作、社内イベント運営、フィードバックシステム構築など初期投資が大きく、特に中小企業にとっては負担が重くなることがあります。短期的には人的リソースや予算が割かれるため、他の緊急施策とのバランス調整が難しくなる点にも注意が必要です。
デメリット2. インナーブランディングで価値観のズレが表面化
企業理念やビジョン、バリューを従業員に強く打ち出すと、それまで曖昧だった社内の価値観の違いや、個々人の仕事観とのギャップが浮き彫りになります。結果として、「なぜ自分はこの会社で働いているのか」「この価値観に本当に共感できるのか」といった葛藤が生まれ、組織内での摩擦や不協和音が増加する可能性があります。共感できない層が増えると、逆に離職リスクが高まり、職場の士気低下を招くケースもあります。ただし、ズレをあらかじめ認識しフォローアップを行うことで、組織の健全化と価値観の調整にもつながります。
デメリット3. インナーブランディングは短期的な成果が見えにくい
インナーブランディングは、社員の行動変容や企業文化の醸成を目的とするため、数値化しづらい「心理的満足度」や「組織の一体感」といった定性的な成果が中心になります。KPIやアンケートで定期的に測定しても、短期間では劇的な変化が現れにくく、経営層への説明や投資対効果の提示が難しいのが実情です。そのため、効果が見えないまま施策が中断されたり、別施策へとリソースが流用されたりするリスクがあります。長期視点でコミットし、段階的な成果指標(例:従業員満足度スコア、参加率、定着率など)を設定することで、継続的な評価と改善を図ることが重要です。
インナーブランディングが向いている企業とは?
インナーブランディングは、社内の一体感やブランド理解を深めたい企業に最適です。特に急成長フェーズで組織拡大中の企業では、理念共有を強化し社員同士の連携を図る必要があります。また、多様な働き方やリモート体制を導入している企業では、遠隔地でもブランドメッセージを統一する手段として有効です。加えて、離職率の高さやコミュニケーション不足に悩む企業は、価値観の再確認と共感醸成を通じて課題解消につながります。こうした企業では、長期視点で文化醸成を進めるインナーブランディングが、安定的な組織運営と企業価値向上に寄与します。
インナーブランディングの進め方、具体例
インナーブランディングは、現状分析と目標設定から始まり、理念・ミッション・ビジョン・バリューの明確化、ブランドコンセプト作成、コミュニケーション戦略構築、社内浸透、最後に評価と改善という6つのステップで進めるのが一般的です。以下、各ステップの具体例をご紹介します。
ステップ1. 現状分析と目標設定
まず、従業員アンケートやフォーカスグループを通じて、ブランド理解度やエンゲージメント状況を可視化します。定量的にはNPSスコア、離職率、定着率などのKPIを設定し、基準値を明確に。定性的にはヒアリングで課題や期待を抽出し、「どこをどう改善するのか」を具体化します。このフェーズで目指すゴールを社内で共有し、全員が同じ旗を掲げられるようにすることが、後続ステップの成功を左右します。
ステップ2. 企業理念・ミッション・ビジョン・バリューの明確化
次に、経営陣と人事、現場リーダーが連携して、企業の核となるMVVを言語化します。曖昧だった言葉に定義を与え、数値目標や行動指針も併記します。社内ワークショップで全社員に「なぜそれが大切なのか」を体感させ、事例ワークやロールプレイを通じて自分ごと化を促進します。これにより、理念が単なるスローガンではなく、日々の判断基準として根づきます。
ステップ3. ブランドコンセプトを作成する
企業理念をベースに、ストーリーテリングの手法でブランドコンセプトを組み立てます。ターゲットと社員のペルソナを定義し、感情に響くメッセージやビジュアル要素を統一。社内向けパンフレット、イントラ動画、ポスターなど多様なフォーマットで制作し、目に触れる機会を増やします。また、キーメッセージを盛り込んだ社内SNSスタンプや壁掲示を導入し、日常業務の中で自然と刷り込まれる仕組みを作ります。
ステップ4. コミュニケーション戦略の構築
社内情報共有チャネル(イントラ、チャットツール、社内報)を整理し、施策ごとに最適なメディアを選定します。全社ミーティングでの動画配信や、部門別フォローアップセッションなど、双方向コミュニケーションを重視します。さらに、管理職向けトレーニングやUBT(ユニバーサル・ブランド・トレーニング)を実施し、社内リーダーが自ら発信できる体制を整備します。ナッジ理論を活用し、小さな成功体験を定期的に共有します。
ステップ5. 社内に浸透させる
全社員が参加できるワークショップやオンラインイベントなどを定期開催し、ブランドメッセージを繰り返しインプットします。部門ごとにアンバサダーを選定し、現場での成功事例を共有するサイクルを確立します。日報・週報フォーマットに「ブランド貢献エピソード」を組み込むことで、日々の業務でどのように体現できたかを振り返る場を創出します。これにより、言語化された理念が行動にまで落とし込まれます。
ステップ6. 評価と改善
半年〜1年ごとにアンケートやNPS調査を実施し、スコア推移をモニタリングします。KPIと照らし合わせて、施策の効果を定量・定性両面から評価します。得られたデータをもとにワークショップ内容やコミュニケーションチャネルを見直し、次のサイクルに反映します。成果や課題は経営会議で定期報告し、経営レベルでのコミットメントを維持し続けることが重要です。
インナーブランディングを効果的にする5つのポイント
インナーブランディングを効果的に実践するには、①課題・目標の明確化・数値化、②長期的な計画とPDCAサイクル、③経営層のコミットメント獲得、④従業員視点での施策設計、⑤忍耐強い継続の5つのポイントが不可欠です。これらを意識することで、施策の方向性がぶれず、効果測定や改善がスムーズに進み、社内文化を醸成しながらブランド価値を高めることができます。
ポイント1. 課題・目標を明確化・数値化する
インナーブランディングの成功には、まず現状分析に基づく課題抽出と、具体的な数値目標設定が欠かせません。例えば、従業員満足度や離職率、社内アンケートのブランド理解度などのKPIを定義し、ベンチマークと比較しながら進捗を可視化しましょう。目標が定まると、施策の優先順位付けやリソース配分が明確になり、社内の合意形成がスムーズになります。
ポイント2. 長期的な計画を立てPDCAをまわす
インナーブランディングは短期的成果が見えにくいため、数年単位の長期計画立案が必要です。具体的には、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)のPDCAサイクルを組織に定着させ、四半期ごとに評価指標を見直しましょう。継続的な改善を通じて施策精度が高まり、時間経過とともにブランド浸透度が向上します。
ポイント3. 経営層に理解してもらう
経営層の強力な後押しとコミットメントがなければ、インナーブランディングは形骸化しがちです。経営指標と直結する成果(生産性、定着率、顧客満足度向上など)を示し、投資対効果をデータで訴求しましょう。さらに、定期的な報告会やワークショップに経営層が参加する仕組みを作り、施策の可視化と意思決定を加速させます。
ポイント4. 従業員に受け入れられる形で行う
いくら理論的に優れた施策でも、従業員に刺さらなければ意味がありません。現場の声を反映したワークショップやストーリーテリング、ゲーミフィケーションを取り入れ、楽しみながら学べる仕組みを構築しましょう。また、成功事例やアンバサダーの声を社内SNSでシェアすることで、自発的な参加と共感を促進できます。
ポイント5. すぐに効果が出なくてもあきらめない
インナーブランディングは企業文化を育む長期戦です。初期フェーズで施策が定着せずとも、成果を焦らず継続的にコミュニケーションを重ねることが重要です。小さな成功体験を積み重ね、フィードバックを元に施策を修正しながら、組織にブランドマインドを根づかせましょう。
インナーブランディングにおける従業員の状態と代表手法
インナーブランディングを向上させると、さまざまな面で企業に利益をもたらすことを説明してきました。ここからは、従業員の状態に対応した具体的な施策について詳しく説明していきます。

ステップ1. 認知・共有
施策としては、全社員を対象にした発表会(説明会)での告知が代表的です。ブランディングは、一部の従業員ではなく、すべての従業員に関わることですので、全員にもれなく伝える平等性が大切です。ツールとしては、定めたブランドコアをより深く知る、ブランドブック、ブランドムービー、クレドブックなど「ブランドのバイブル」を配布。このステップでは、初めて聞いて知ることばかりで、ようやく頭で「こういったブランドを目指す」、「ブランドコア / P-MVV(パーパス・ミッション ビジョン バリュー)」がわかった段階です。
ステップ2. 理解・共感
社内での対話、チームビルディングやワークショップを通じて、各社員に心で理解することを促します。経営トップからの強いメッセージングもこのステップでは重要です。根気良く伝え続けることがトップには求められます。
ステップ3. あるべき姿を「自分ごと化」
頭と心で理解することと、実際の行動に移せることではかなりのギャップがあるため、このステップが必要になります。具体的には各自およびグループに目標宣言や行動宣言を行ってもらうケースが多いです。新たなブランドコア / P-MVV(パーパス・ミッション ビジョン バリュー) 等を受け、自分は何を変えるべきか、部署としてどんな取り組みをすべきかをチームビルディングやワークショップなどで話し合い、全社員に向けて宣言化するのです。また、宣言しっぱなしでは定着しにくいため、社内のイントラサイトなどで活動を共有するなど、行動を見える化する仕組みも必要となります。
ステップ4. 評価・奨励
社員が自ら宣言して行動したことを褒めることで、何が正しいことなのかを全従業員に示してあげることが目的です。これを繰り返していくことで、ブランドが企業の体質となり、新たな取り組みも生まれてきます。具体的な施策としてはアワードなどを設立し、表彰することで「もっとやりたくなる状態」を目指します。場合によっては人事評価やその他インセンティブと結びつけられることもできますが、自ら取り組みたくなるようにすることが肝心なので、社員にとって誇らしくかつ楽しい取り組みを用意しましょう。
インナーブランディングの効果的な12の手法
企業が採用できるインナーブランディングの手法は、社内イベントの開催、ビジョン・ミッション・バリュー浸透プログラム、イントラネットやチャットツールなどのコミュニケーションプラットフォーム活用など、多岐にわたります。これらに加え、管理職向けトレーニングやストーリーテリングを通じた価値共有、アンケートによるフィードバックサイクルの構築、表彰制度の導入など、社員の主体性を引き出す仕組みが効果的です。さらに、社内メディア運営や顧客フィードバック活用、ワークショップ/ブレインストーミング、トップメッセージ発信、クレド策定といった12の具体手法を組み合わせることで、理念を実践に落とし込み、企業文化の深化を図ることができます。
手法1. 社内イベントの開催
インナーブランディングの定番手法として、社内イベントは効果抜群です。ゲームやグループワークを取り入れ、部署を越えた交流を促進します。周年記念や社員総会では、ブランド理念を体現するワークショップを組み込むことで、一体感と理解が深まります。
手法2. ビジョン・ミッション・バリューの浸透プログラム
社内研修やeラーニングを活用し、企業のビジョン・ミッション・バリュー(MVV)を段階的に学べるプログラムを実施します。ケーススタディやロールプレイで「自分ごと化」を促し、理念が日常行動に結びつく仕組みを構築します。
手法3. 社内コミュニケーションツールの活用
社内コミュニケーション強化の一環として、企業はイントラネットや社内SNS、チャットツールを通じてMVVに関する投稿や成功体験を積極的に共有します。その結果、リアルタイムでのフィードバックや意見交換が常態化し、ブランド情報が日々社員に届く仕組みが整います。また、部署を越えたオープンチャネルを活用することで部門間の交流が活性化し、異なる視点からのアイデアやコラボレーションが促進されます。
手法4. 管理職・リーダー向けトレーニング
管理職やチームリーダーを対象に、ブランドメッセージの伝え方やコーチング技法を習得させる研修を実施します。リーダー自身がアンバサダーとして社内に発信することで、全体への波及効果を高め、施策の定着を支援します。
手法5. ストーリーテリングの活用
ブランドや理念を物語形式で伝えるストーリーテリングは、感情に訴えかける強力な手法です。創業秘話や社員の成功体験を動画や社内報で紹介し、具体的なエピソードを共有することで、ブランド理解と共感を一層深めます。
手法6. 社内アンケートとフィードバック
組織では定期的にアンケートを実施し、従業員の理解度や満足度を数値化して全社に共有します。そこから浮かび上がった改善点や成功事例を具体的な施策に落とし込むことで、双方向のコミュニケーションが自然に育まれます。こうした透明性の高いフィードバックの仕組みは、従業員との信頼関係を着実に強化します。
手法7. 表彰制度の導入
ブランド理念を体現した行動を表彰する制度を設けることで、模範となる事例を可視化できます。月間・年間MVPや「バリュー賞」など、具体的な称号とインセンティブを用意すると、全社員のモチベーションを高めるきっかけになります。
手法8. 社内メディアの活用
社内報やイントラマガジン、動画チャンネルなど多様なメディアを活用し、ブランド情報を定期的に発信します。特集記事やインタビューで経営層の想いを伝えたり、部門横断のプロジェクトレポートを掲載することで、社員の関心を喚起します。
手法9. 顧客からのフィードバック活用
顧客満足度調査やレビューを社内で共有し、顧客視点でのブランド価値を実感してもらうことができます。成功事例や改善要望をもとに社内ディスカッションを行うことで、社員が「顧客に届くブランド」を肌感覚で理解できます。
手法10. ワークショップやブレインストーミングセッション
テーマごとのワークショップやブレインストーミングを定期的に開催し、社員自らがブランド施策を企画・提案します。主体的な参加が価値観の内面化を促し、社員発信のアイデアがブランド活動の多様化と活性化を後押しします。
手法11. トップメッセージ
代表や経営層からのトップメッセージは、ブランド施策における権威付けとなります。定期的な全社メールや動画配信、ライブQ&Aで企業の方向性を語り、従業員の疑問に答える場を設けることで、信頼感と納得感が高まります。
手法12. クレド
行動指針をまとめたクレドを策定し、ポスターやカードで常に掲示します。日常業務の合間に手に取りやすい形で配布すると、価値観の確認や行動基準が自然と意識されます。チーム単位のクレド活動やローカライズも効果的です。
成功事例から読み解くインナーブランディング
インナーブランディングは社内で行われているプロジェクトのため、なかなか想像がつかない方も多いはずです。そこでまずは、有名企業の成功事例を見ていきましょう。
事例1. スターバックス
「ブランディングの優良企業」というイメージがあるスターバックスですが、やはりインナーブランディングにも力を入れています。
スターバックスは、「The Third Place」(自宅でも職場でもない「第三の場所」)というブランドのコアを掲げ、プロダクトやサービス、店舗空間、社員教育等を徹底し、一貫性のある「おもてなし」で、顧客にとって真に心安らぐ場を提供してきました。
しかし、2007年から2008年にかけて、売上高は増えているものの、利益が半減したことがありました。その原因は、既存店での売上高の伸び率がマイナスになったことです。多くの経営者は、経営合理化による利益率向上策を採用するところですが、スターバックスの窮地を救うべくCEO に復帰した、創業者のハワード・シュルツ氏の採った策は「原点回帰」でした。

当時のスターバックスでは、迅速にコーヒーを提供するために別の場所にあるセンターで豆を挽いており、さらに店舗急拡大で、教育が不十分なバリスタが店頭に立つようになってしまい、コーヒーの味が落ちてしまったのです。そこでシュルツ氏は、無駄があってもかまわないから「スタバらしさ」を取り戻そうと決意したのでした。
まず、当時全米にあった 7100 店舗を一斉に半日閉店し、バリスタの再研修を実施しました。年商に響くレベルでの売上減少は確実でしたが、それも覚悟の上の決断です。さらに新しいブレンドコーヒーを開発し、最高級のコーヒーを入れるためのマシン会社を買収し、店舗でコーヒー豆を挽く方式に戻したのです。しかしそれ以上に力を入れたのは、「スタバらしさとは何か? それを実現するために自分は何ができるのか?」を徹底的に考え続ける社内研修、すなわち「インナーブランディング」だったのです。
こうした施策の結果、スターバックスは再生し、今も成長を続けています。米インターブランド社による 2021 年の世界ブランドランキングでは 51 位、ブランド価値は 130.1 億米ドル(1 ドル=130 円として、16 兆 9130 億円)と見積もられています。
事例2. メルカリ
コロナ禍でリモートワークが標準化し、密なコミュニケーションを取れないために会社の方向性を伝えにくくなり、社員のエンゲージメントが低下していると言われています。エンゲージメントの向上はインナーブランディングにおいても重要なポイント。そこで有効な策として、社内サイトによる社内コミュニケーションの活性化が挙げられます。
メルカリは、「mercan」という社内報にあたるコンテンツを配信する、オウンドメディアを持っていて、これは一般の方でも見られるようになっています。メルカリグループのメンバーであれば誰でも発信ができるコンテンツプラットフォームで、テキストはもちろん、音声、動画など様々な形式のコンテンツを発信できるようになっています。、そしてこれは、インナーブランディングだけでなくアウターブランディングの活動の一部でもある広報としての効果があるとされています。会社内の透明性が評価される時代において、社内サイトは社外に対してこんな会社だということを伝える接点として重要さを増しています。
ここで注意すべきなのは、インナーブランディングが十分にできていないまま、社外に発信してしまうと、逆にブランドを毀損してしまう内容を発信してしまう可能性もあります。会社内の透明性が求められる時代において、社内サイトは社外に対しこんな会社だということを伝える接点として有効に活用していきましょう。
インナーブランディングのよくある失敗事例
インナーブランディングを行おうとしても、なかなか上手くいかない企業も少なくありません。弊社でも企業様から様々なご相談をいただく中で、そういった企業様に共通して見られるポイントをまとめました。
失敗要因1. 作って満足し、そのまま放置
インナーブランディングを行う上で、ブランドブックやクレドカードなどのアウトプットまで制作したにも関わらず、そのまま放置され、結果浸透されないことが多々あります。本来インナーブランディングは短期間ではなく、中長期的に腰を据えて行うべきものですので、浸透のための施策を行わず、短期的なスパンで実施しようとすると失敗してしまうのです。内容を理解した上でそれを咀嚼し、自分ごとにするためには、ブランドコア / P-MVV(パーパス・ミッション ビジョン バリュー)、チームビルディング、オフィスデザインといったアウトプットを制作した上での丁寧な社内コミュニケーションや体験の機会が必要です。
失敗要因2. 推進している人が不明確
インナーブランディングに取り組んでいること自体は知っているけれど、誰が推進しているのかがわからないことが意外と多いです。そこで重要なのが、社内に企業理念やブランドメッセージ、キャッチコピーを浸透させるアンバサダーの存在です。トップからだけでなく”隣”からじわじわと広めることで、社員の共感度を高め、自律的な組織を作ることに繋げる重要な役割があります。
失敗要因3. トップのみによる推進
企業トップだけのリーダーシップで進めていくと、義務に感じる社員が生まれ、「命令だからやる」と思考停止をしてしまう可能性が高くなります。よくある事例は、従業員の理解や納得を得るプロセスが不十分な状態のまま、ワークショップや制度など従業員の行動に直結するアプローチを行い、拒否反応や強い抵抗が起きてしまうというものです。従業員に企業理念やブランドメッセージ、キャッチコピーを浸透させるためには、従業員の声をインプットすることが最重要です。ブランディングの取り組みを自分ごと化してもらうためには、社員の自主性を尊重し、社員が常に考え続ける、ボトムアップ型も同時に取り入れることが大切です。
まとめ
自社の魅力を社外へ発信していくには、まずは社員一人一人がインナーブランディングの活動を通して自社を理解し、エンゲージメントを高めていく必要があります。それらを行うことで、働く人のモチベーションの維持や人材流出の低減など、様々な課題解決に結びつきます。ブランディングを始めるには、まずはインナーブランディングから検討してみてはいかがでしょうか。
【参考文献】
『手にとるようにわかる ブランディング入門』(金子大貴著、 一色俊慶著)
東洋経済オンライン社:よみがえったスタバに学ぶ、「らしさ」の経営
https://toyokeizai.net/articles/-/49204
『スターバックス再生物語 繋がりを育む経営』(ハワード・シュルツ、ジョアンヌ・ゴードン著、月沢季歌子訳、徳間書店)

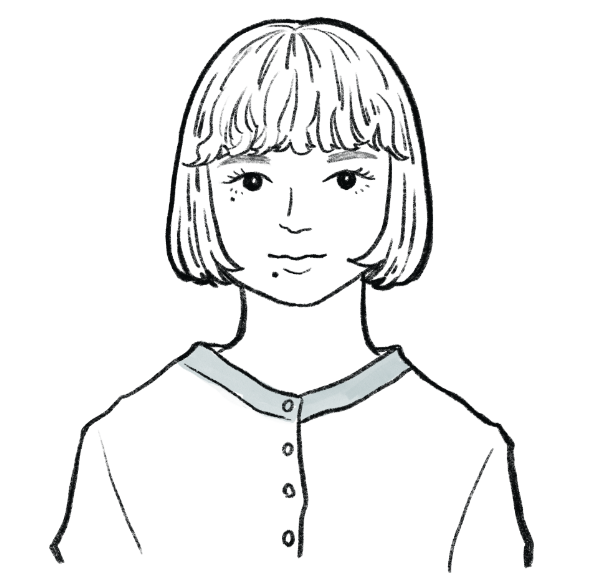

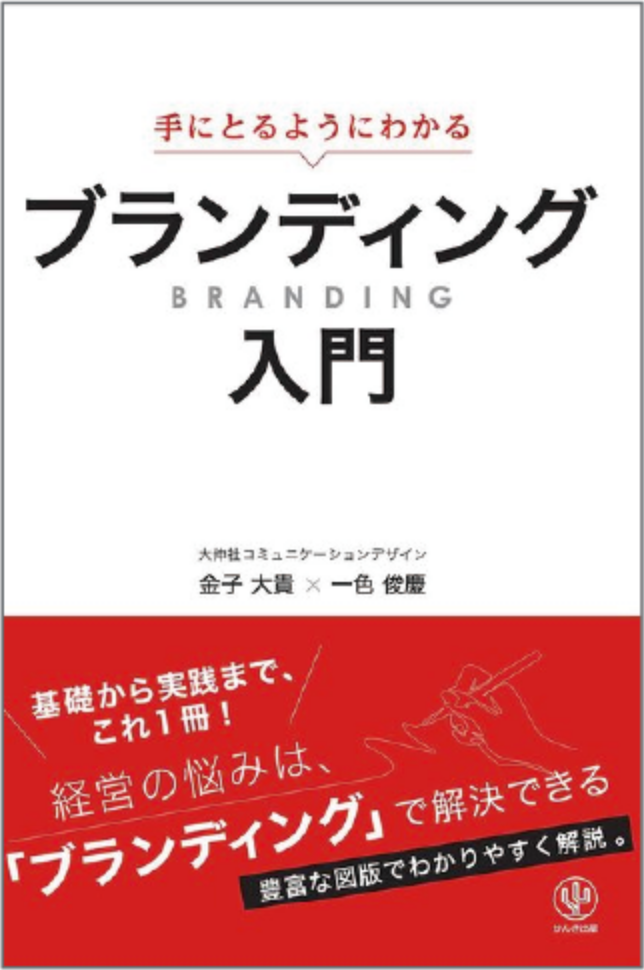 株式会社 大伸社コミュニケーションデザイン チーフ ブランディングディレクター コピーライターとして、広告・宣伝のクリエイティブ開発の経験を経て、ブランディングに特化したプランニング・コンサルティングを担う現職へ。大手上場企業から中小企業まで、企業のリブランディングプロジェクト、新製品のコンセプト開発、ブランド浸透戦略立案などの幅広い業種業態でのブランディング支援を実施。
株式会社 大伸社コミュニケーションデザイン チーフ ブランディングディレクター コピーライターとして、広告・宣伝のクリエイティブ開発の経験を経て、ブランディングに特化したプランニング・コンサルティングを担う現職へ。大手上場企業から中小企業まで、企業のリブランディングプロジェクト、新製品のコンセプト開発、ブランド浸透戦略立案などの幅広い業種業態でのブランディング支援を実施。